介護の仕事を意気込んで始めた初日、「もう辞めたい…」と心が折れそうになっていませんか。
慣れない環境、想像を絶する業務内容、そして先輩職員との微妙な距離感。
その絶望的な気持ち、異常ではありません。
むしろ、多くの人が通る道であり、極めて自然な反応です。
私自身、10年以上にわたり様々な介護施設を渡り歩いてきましたが、初日のあの独特な空気感と疲労感は今でも鮮明に覚えています。

この記事では、元介護士で現在は施設の事務職として現場を見守る私が、なぜ介護の初日に辞めたくなるのか、その根本的な原因を解き明かします。
そして、その辛い状況で「仕事を続けるべきか」「思い切って見切るべきか」を冷静に判断するための、具体的な基準をあなたに提示します。
この記事を読み終える頃には、あなたの心の中のモヤモヤが晴れ、次にとるべき行動が明確になっているはずです。
なぜ多くの人が介護の初日に「辞めたい」と感じるのか?
介護の初日を終えて「もう辞めたい」と感じてしまうのは、決してあなた一人が特別なのではありません。
むしろ、多くの未経験者や経験者でさえもが、同じような感情を抱くことがあります。
私自身も、初めて特養の門を叩いた日のことは忘れられません。
ここでは、多くの人が初日に心が折れそうになる、その背景にある共通の原因を、私の経験も交えながら深掘りしていきます。

想像以上だった…「きつい・無理」と感じる心身への負担
介護の仕事に対して、ある程度の覚悟はしていたはず。
それでも、初日に体験する現実は、その想像をはるかに超えてくることが少なくありません。
特に、心と体への負担は、多くの新人が「きつい」「無理かもしれない」と感じる直接的な原因となります。
精神的な「きつさ」の正体
介護の現場で求められる精神的な強さは、他の多くの職業とは質が異なります。
例えば、認知症の利用者様とのコミュニケーションです。
一生懸命に話しかけても、思いが伝わらなかったり、時には厳しい言葉を投げかけられたりすることもあります。
新人であればあるほど、一つ一つの言動に傷つき、「自分は向いていないのではないか」と深く悩んでしまうのです。
また、常に「命を預かっている」というプレッシャーも、見えないストレスとしてのしかかります。
身体的な「きつさ」の現実
肉体的な負担も想像以上です。
特に移乗介助(ベッドから車椅子へ、など)は、コツを掴むまでは完全に体力勝負。
小柄な女性スタッフが、自分よりも大きな男性の利用者様を支える光景は日常茶飯事です。
腰への負担は深刻で、初日を終えただけで全身が筋肉痛になることも珍しくありません。
私がいた有料老人ホームでは、比較的自立度の高い方が多かったですが、それでも一日に何度もナースコールが鳴り、フロアを走り回るため、一日の終わりには足が棒のようになっていました。
こうした心身両面からの負担が、初日にして「続けられない」という結論に結びついてしまうのです。
「聞いていた話と違う」理想と現実のギャップと独特の人間関係
面接や求人票で聞いていた職場環境と、実際に足を踏み入れた現場の空気が全く違う、というのも「介護あるある」の一つです。
このギャップが、不信感や孤立感を生み、早期離職の引き金となります。

理想と現実の大きな溝
「アットホームで和気あいあいとした職場です」という言葉を信じて入職したのに、実際は職員同士の私語はほとんどなく、業務連絡だけが飛び交う殺伐とした雰囲気だった、というケースは少なくありません。
また、「未経験者でも安心の研修制度あり」と謳われていながら、実際は「見て覚えて」の一点張りで、右も左も分からないまま放置されることもあります。
このような状況では、「騙された」と感じてしまうのも無理はありません。
介護現場特有の人間関係
介護現場は、様々な年代や経歴を持つ人が集まる場所であり、その人間関係は非常に濃密になりがちです。
特に女性が多い職場では、独自のグループや力関係が存在することも珍しくありません。
新人は、その輪の中にどう入っていけば良いのか分からず、戸惑ってしまうことが多いのです。
先輩たちの何気ない会話の一つ一つが、自分への評価に繋がっているのではないかと勘繰ってしまい、精神的に疲弊していきます。
この独特の人間関係に馴染めないことが、「仕事そのものよりも、人間関係が理由で辞めたい」という気持ちに繋がっていくのです。
なぜ?介護職で新人が放置されてしまう、よくある理由
初日に最も辛いことの一つが、「放置」されることです。
何をすればいいのか分からず、ただただ時間が過ぎるのを待つだけの時間は、自己肯定感を著しく低下させます。
では、なぜこのようなことが起こってしまうのでしょうか。
決して、先輩たちが意地悪で放置しているわけではないケースも多いのです。
施設の事務員として運営側から現場を見ていると、いくつかの構造的な問題が見えてきます。

慢性的な人手不足で教える余裕がない
これが最も大きな理由です。
多くの介護施設は、ギリギリの人数で現場を回しています。
一人のスタッフが複数の利用者様を担当しており、常に時間に追われています。
そんな中で、新人に付きっきりで業務を教える時間的・精神的な余裕が全くないのが現実です。
「後で教えるから、ちょっと待ってて」と言われたまま、結局終業時間になってしまった、という悲しい事態は、残念ながら頻繁に起こります。
「見て覚えろ」という古い教育体制
特に古くからある特別養護老人ホームなどでは、体系的な新人研修プログラムが存在せず、「仕事は先輩の背中を見て盗むものだ」という文化が根強く残っている場合があります。
マニュアルが整備されておらず、教える側の先輩によってやり方が違うことも多々あります。
これでは、新人は誰の言うことを信じれば良いのか分からず、混乱してしまいます。
これは、教え方が悪いという個人の問題だけでなく、施設全体の教育に対する意識の低さが原因なのです。
新人の受け入れに慣れていない職場
意外に思われるかもしれませんが、長年スタッフの入れ替わりがなかった職場では、そもそも「新人にどうやって教えればいいか分からない」という状況に陥っていることがあります。
久しぶりに入ってきた新人に対して、どう接していいか分からず、結果的に距離ができてしまい「放置」という形になってしまうのです。
「介護職はやめとけ」と言われるのは本当?辞める人が多い職場の実態
インターネットなどで情報を集めていると、「介護職はやめとけ」という言葉を目にすることがあるかもしれません。
そして初日に強烈な洗礼を受けると、「あの言葉は本当だったんだ…」と絶望的な気持ちになるでしょう。
確かに、介護業界は離職率が高いと言われており、介護労働安定センターの調査でもその傾向は見られます。

しかし、全ての職場がそうではありません。
問題なのは、「辞める人が多い職場」には、いくつかの共通した特徴があるという点です。
あなたが初日で「辞めたい」と感じた職場は、もしかしたら「辞める人が多い職場」、つまり俗に言う「ブラックな施設」なのかもしれません。
例えば、職員の愚痴や不満が常に飛び交っている、明らかに清掃が行き届いておらず不潔、利用者様への言葉遣いが乱暴、といった特徴が見られる職場は要注意です。
こうした職場では、新人へのサポート体制が整っているはずもなく、多くの人が早い段階で辞めていく傾向にあります。
つまり、「介護職」という仕事そのものが悪いのではなく、あなたが足を踏み入れた「職場環境」に大きな問題がある可能性が高いのです。
私も経験しました。特養と有料老人ホームでの初日の違い
ここで、私の個人的な経験をお話しさせてください。
私はこれまで、特別養護老人ホーム(特養)と有料老人ホームの両方で働いた経験がありますが、同じ「介護職」でも、初日の衝撃は全く異なるものでした。
この違いを知ることは、あなたが今感じている辛さが、その職場特有のものなのかを判断する一助になるはずです。

特養の初日:「戦場」という言葉がふさわしい場所
私が初めて介護士として働いたのは特養でした。
初日の感想を一言で言うなら、「戦場」です。
朝の申し送りが終わるやいなや、先輩たちは猛烈なスピードで動き出します。
オムツ交換、食事介助、入浴介助…次から次へと業務が押し寄せ、ゆっくりと質問をする隙もありません。
利用者様の要介護度も高く、ほぼ全介助の方が多かったため、常に時間との戦いでした。
ここでは、効率とスピードが何よりも重視され、「見て、早く覚えて、戦力になって」という無言のプレッシャーをひしひしと感じたことを覚えています。
丁寧さよりも、まずは業務をこなすことが求められる環境でした。
有料老人ホームの初日:お客様への「おもてなし」の視点
一方、有料老人ホームの初日は全くの別世界でした。
もちろん忙しさはありますが、特養のような「戦い」という雰囲気ではありません。
利用者様は「入居者様」「お客様」と呼ばれ、言葉遣いや立ち居振る舞いにも、ホテルマンのような丁寧さが求められました。
初日は、まず一人ひとりの入居者様の居室を回り、ご挨拶をすることから始まりました。
業務内容も、集団ケアというよりは、その方の生活スタイルに合わせた個別ケアが中心です。
ここでは、スピードよりも「その方らしい生活をどう支えるか」という視点が重要視されていると感じました。
このように、同じ介護の仕事でも、施設形態が違えば、求められるスキルも、職場の文化も、初日に感じるプレッシャーの種類も全く異なるのです。
あなたが今いる場所が、たまたまあなたに合わないタイプの施設だった、という可能性も十分にあるのです。
介護の初日に「辞めたい」と思ったら。続けるか見切るかの判断基準
初日を終えて「もう辞めたい」という気持ちでいっぱいになっている今、感情的に行動してしまうのは得策ではありません。
一度立ち止まり、冷静に状況を分析することが、あなたのキャリアにとって非常に重要になります。
ここでは、その辛い気持ちをどう乗り越え、今後どうすべきかを判断するための具体的な基準と行動指針を、私の経験を基に解説していきます。

1日で辞めたとしても大丈夫。まずは冷静に原因を分析しよう
まず、あなたに一番伝えたいこと。
それは、たとえ1日で辞めることになったとしても、あなたの人生が終わるわけでは全くないということです。
むしろ、合わない環境で心身をすり減らし続けることの方が、よほど大きな損失です。
ですから、自分を責めるのは今日で終わりにしましょう。
その上で、なぜ「辞めたい」と強く感じたのか、その原因を客観的に分析することが大切です。
感情のままでは、正しい判断はできません。
ノートとペンを用意して、以下の二つの視点から、辞めたい理由を書き出してみてください。
①自分自身に原因があると感じること
- 仕事の覚えが悪く、迷惑をかけていると感じる
- 想像していたよりも、体力的にきつい
- 利用者様とのコミュニケーションがうまく取れない
- そもそも介護という仕事への覚悟が足りなかったかもしれない
②職場環境に原因があると感じること
- 初日から放置され、何をすればいいか分からなかった
- 先輩の教え方が悪い、もしくは誰も教えてくれない
- 職場の人間関係が悪そうで、雰囲気が気まずい
- 面接で聞いていた話と、実際の労働条件や仕事内容が違う
このように書き出して可視化することで、自分の感情を客観的に見つめ直すことができます。
もし原因が①に偏っているなら、もう少し頑張ることで乗り越えられる可能性があります。
しかし、②の要素が強いのであれば、それはあなたの努力だけではどうにもならない、「見切るべき職場」のサインかもしれません。
これは危険信号?退職者が続出する、すぐに見切るべき職場の特徴
介護の仕事を10年以上続けてきた経験から、新人がすぐに辞めてしまう、いわゆる「退職者が続出する職場」には、いくつかの明確な危険信号(レッドフラグ)があることが分かっています。
もし、あなたの職場が以下の項目に複数当てはまるのであれば、それはあなたの甘えや努力不足ではなく、職場そのものに深刻な問題がある証拠です。
あなたの心と体を守るためにも、早期の退職を真剣に検討すべきです。

職員の表情が暗く、悪口や愚痴が蔓延している
これは最も分かりやすいサインです。
職員休憩室やスタッフルームで、利用者様や他の職員の悪口、会社への不満ばかりが聞こえてくるような職場は、間違いなく健全ではありません。
職員が精神的に追い詰められており、お互いを尊重する文化が失われています。
このような環境では、新人が安心して成長することなど到底不可能です。
明らかな法令違反や倫理観の欠如が見られる
例えば、サービス残業が当たり前になっている、休憩時間が全く取れない、といった労働基準法違反が常態化している職場は論外です。
また、利用者様に対して「ちゃん」「じいさん、ばあさん」といった不適切な呼び方をしたり、介助が乱暴だったりするなど、職業倫理が欠如している場面を目撃した場合も、即座に見切りをつけるべきです。
そうした行為が許される環境に身を置くことは、あなた自身の倫理観をも麻痺させてしまいます。
教育・研修制度が名ばかりで、初日から放置される
前述の通り、人手不足を理由に新人教育を放棄している職場です。
「見て覚えろ」という名の放置は、教育ではなく、ただの怠慢です。
このような職場では、あなたが成長できないだけでなく、いつか大きな事故を起こしてしまうリスクすらあります。
あなたの安全と利用者様の安全を守るためにも、教育体制が機能していない職場からは離れるべきです。
試用期間での退職は可能?円満に辞めるための伝え方と手順
「まだ試用期間なのに、辞めるなんて言えるのだろうか…」と不安に思うかもしれません。
結論から言えば、試用期間中の退職は法的に全く問題ありません。
試用期間は、労働者がその職場に適応できるかを見極める期間であると同時に、労働者側が「この職場で働き続けられるか」を見極めるための期間でもあります。
ただし、社会人としてのマナーを守り、できる限り円満に退職手続きを進めることが、次のステップへ気持ちよく進むために重要です。
決して、無断で連絡を絶つ「バックレ」だけは避けてください。
給料が支払われないリスクがあるだけでなく、狭い介護業界で悪い評判が立つ可能性もゼロではありません。

円満退職のための3ステップ
- 直属の上司に口頭で伝える
まずは、直属の上司(主任やフロアリーダーなど)に「お話があるのですが、少しお時間をいただけますでしょうか」とアポイントを取ります。そして、必ず対面で退職の意思を伝えてください。電話やLINEで済ませるのはマナー違反です。 - 退職理由は「一身上の都合」で十分
退職理由を正直に話す必要はありません。「職場の人間関係が…」「教育体制が…」などと不満を述べても、引き止めに合うだけで、お互いに良い気持ちはしないでしょう。シンプルに「一身上の都合により、退職させていただきたく存じます」と伝えれば十分です。もし深く理由を聞かれた場合でも、「熟慮の結果、自分の力不足を痛感し、このままご迷惑をおかけすることはできないと判断いたしました」といったように、あくまで自分起因の形にすると、波風が立ちにくいです. - 退職届を提出する
口頭で伝えた後、会社の規定に従い退職届を提出します。フォーマットがなければ、白い便箋に手書き、あるいはPCで作成したもので問題ありません。提出日、退職日、自分の氏名・捺印、宛名(会社の代表者名)を明記し、退職理由はここでも「一身上の都合」とします。
初日で辞めるのは非常に気まずいと感じるでしょう。
しかし、これはあなたのキャリアを守るためのビジネスライクな手続きです。
毅然とした態度で、事務的に進めることを心がけてください。
もう少し頑張れそうなら。介護職が続く人の考え方と仕事のコツ
一方で、「職場環境は最悪というわけではない」「もう少しだけ頑張ってみたい」という気持ちが少しでもあるなら、もう少しだけ続けてみる価値はあるかもしれません。
介護の仕事は、最初の壁を乗り越えると、大きなやりがいや喜びに変わることがあるのも事実です。
ここでは、介護職を長く続けている人が実践している、仕事への向き合い方や考え方のコツを紹介します。

「100点満点」ではなく「60点」を目指す
特に真面目で責任感の強い人ほど、初日から完璧に仕事をこなそうとして、自分で自分を追い詰めてしまいます。
しかし、新人が最初から100点満点の仕事などできるはずがありません。
まずは「今日教わったことを一つでも確実にやる」「利用者様の顔と名前を一人覚える」など、今日の目標は60点で合格、と考えるようにしましょう。
この「完璧主義をやめる」という考え方は、長く仕事を続ける上で非常に重要なメンタルコントロール術です。
「教えてもらうプロ」になる
先輩たちが忙しそうにしていると、質問するのも気が引けてしまいますよね。
しかし、分からないまま仕事を進めることの方が、後々大きな迷惑に繋がります。
大切なのは、質問の仕方を工夫することです。
「お忙しいところ申し訳ありません。今、1分だけよろしいでしょうか?」「〇〇の件で一点だけ確認させてください」など、相手への配慮を示す一言を添えるだけで、印象は大きく変わります。
受け身で待つのではなく、自分から学ぶ姿勢を見せることが、結果的にあなたの成長を早め、周囲との関係を良好にします。
仕事のスイッチを完全にオフにする時間を作る
仕事の悩みを家に持ち帰らないこと。
これは、心身の健康を保つために不可欠です。
休日は、介護のことは一切考えず、自分の好きなことに没頭する時間を作りましょう。
美味しいものを食べる、友人と会う、映画を見る、何でも構いません。
このオンとオフの切り替えが上手な人ほど、ストレスを溜め込まずに仕事を続けることができています。
次の職場選びで失敗しないための3つのチェックポイント
今回の辛い経験は、決して無駄ではありません。
むしろ、「自分に合わない職場がどういうものか」を知ることができた、貴重な経験です。
この学びを次に活かし、あなたに合った職場を見つけるために、次の転職活動では以下の3つのポイントを必ずチェックしてください。
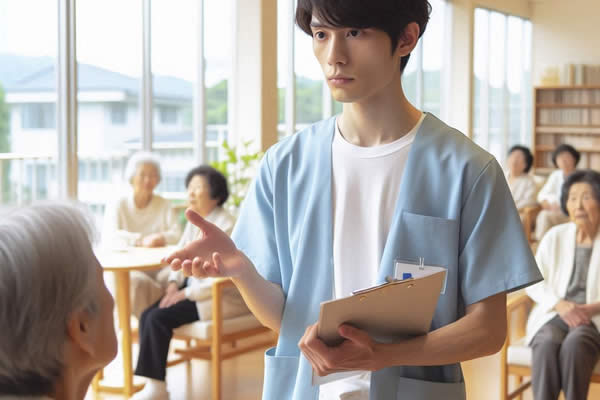
①応募前の「施設見学」は必須
求人票の情報や写真だけでは、職場の本当の雰囲気は分かりません。
応募する前に、必ず施設見学を申し込みましょう。
チェックすべきは、働いている職員の表情です。
スタッフ同士が笑顔で会話しているか、利用者様に対して穏やかに接しているか。
また、施設全体が清潔に保たれているか、掲示物は整理されているか、といった点も、その施設の管理体制や余裕度を測る重要な指標になります。
②面接では「教育体制」について具体的に質問する
面接は、あなたが評価される場であると同時に、あなたが職場を評価する場でもあります。
臆することなく、新人への教育体制について具体的に質問しましょう。
「新人研修はどのようなプログラムで行われますか?」「独り立ちまでの期間の目安はどのくらいでしょうか?」「指導は、どなたか特定の先輩が担当してくださるのでしょうか?」
これらの質問に対して、明確で具体的な回答が返ってくる職場は、新人を大切に育てる文化がある可能性が高いです。
③介護に特化した転職エージェントを活用する
一人で転職活動をするのが不安な場合は、介護業界に特化した転職エージェントの利用を強くお勧めします。
彼らは、一般には公開されていない内部情報(職場の雰囲気、離職率、人間関係など)を把握していることがあります。
あなたの希望や今回の経験を伝えることで、あなたに合った社風の職場を客観的な視点から提案してくれます。
複数のエージェントに登録し、それぞれの担当者から多角的な情報を得るのも有効な手段です。
まとめ:「介護の初日に辞めたい」は、次への大切な一歩
今回は、介護の初日に「辞めたい」と感じてしまう原因と、その後の判断基準について詳しく解説しました。
初日で心が折れそうになるのは、決してあなたの責任ではありません。
むしろ、それはあなた自身が真剣に仕事と向き合っている証拠です。
大切なのは、その辛い気持ちの原因が「自分自身の課題」なのか、それとも「職場の環境問題」なのかを冷静に見極めることです。
もし職場に明らかな問題があるのなら、あなたの心と体を守るために、ためらわずに「見切る」という選択をしてください。
もし、もう少し頑張れそうだと感じるなら、完璧を目指さず、仕事のオンとオフを切り替える工夫をしてみてください。
どちらの道を選んだとしても、今回の経験は「あなたに合う介護の形」を見つけるための、非常に価値のある一歩となります。
この辛い経験を糧にして、あなた自身が納得できるキャリアを築いていかれることを、心から応援しています。




コメント