「訪問介護を始めたけれど、想像以上にきつくて、もう辞めたい…」
「一人で利用者さんのお宅に伺うのが、精神的に限界かもしれない…」
今、この記事を読んでくださっているあなたは、そんな風に悩んでいるのではないでしょうか。
かつて様々な介護現場を渡り歩いてきた私のもとにも、訪問介護の仕事に悩み、「すぐ辞めるべきか」と相談に来る方は少なくありません。

訪問介護をすぐ辞めることは、決して珍しいことではないのです。
しかし、勢いで辞めてしまって後悔しないか、不安に思う気持ちもよく分かります。
この記事では、長年介護業界に身を置き、現在は事務職として現場を客観的に見ている私が、なぜ訪問介護を辞める人が多いのか、その根本的な原因を解き明かします。
その上で、あなたが今後どうすべきか、後悔のない決断を下すための具体的な判断基準を提示します。
この記事を読み終える頃には、あなたの心の中のもやもやが晴れ、次の一歩を踏み出すための道筋が見えているはずです。
- なぜ訪問介護をすぐ辞める人が多いのか?【体験談から見る5つの原因】
- 「訪問介護をすぐ辞める」と決断する前に。後悔しないための判断基準
なぜ訪問介護をすぐ辞める人が多いのか?【体験談から見る5つの原因】
「訪問介護はやりがいがある」と聞いて始めたのに、なぜこんなに早く辞めたくなってしまうのでしょうか。
それは決して、あなたの根性が足りないからではありません。
訪問介護という働き方には、施設介護とは異なる特有の構造的な課題が存在するのです。
私自身、特別養護老人ホーム(特養)や有料老人ホームなど、複数の施設形態を経験した後に訪問介護事業所で働いた経験がありますが、その「違い」に戸惑ったことを今でも覚えています。
ここでは、多くの人が訪問介護を短期間で辞めてしまう主な原因を、私の経験も交えながら5つの視点で深掘りしていきます。

理想と現実のギャップ?多くの介護職がすぐ辞める本当の理由とは
多くの介護職がすぐに辞めてしまう背景には、理想と現実の間に横たわる大きなギャップがあります。
「利用者一人ひとりと、じっくり向き合ったケアができる」
「自分のペースで働けそう」
訪問介護の求人には、こうした魅力的な言葉が並びます。
しかし、実際に働き始めると、思い描いていた理想とは異なる現実に直面することが少なくありません。
ケア以外の「見えない業務」の多さ
私が施設から訪問介護に移って最初に驚いたのが、純粋なケア以外の業務が非常に多いことでした。
利用者さんのお宅から次のお宅への移動時間。
これは当然、給与が発生しない「すきま時間」になりがちです。
一日の大半が移動で終わってしまい、実働時間に見合った収入にならない、というケースは珍しくありません。
また、サービス提供記録の作成も、想像以上に時間を要します。
施設であれば空いた時間に記録ステーションでまとめて書けますが、訪問の場合は移動の合間や帰宅後に作成することも多く、サービス残業の温床になりやすいのです。
こうした「見えない業務」の積み重ねが、心身を疲弊させる大きな原因となります。
想像以上にシビアな利用者宅の環境
施設介護であれば、介護しやすいように整備された環境で働くことができます。
しかし、訪問介護の現場は、利用者さんの「ご自宅」です。
生活スタイルも、衛生観念も、ご家庭によって様々です。
中には、物が溢れていてケアの動線を確保するのが難しいお宅や、衛生的に厳しい環境でサービスを提供しなければならない場面もあります。
もちろん、それもその方の「暮らし」の一部ではあるのですが、整った環境に慣れていると、このギャップに対応するのが精神的にきついと感じる人もいるでしょう。
介護職がすぐ辞める背景には、こうした理想だけでは乗り越えられない、シビアな現実が存在しているのです。
「一人で訪問」が精神的にきつい…訪問介護に特有の孤独感とプレッシャー
訪問介護の最大の特徴は、何と言っても「一人で利用者宅を訪問し、一人でケアを完結させる」という点です。
この「一人」という状況が、想像以上の孤独感とプレッシャーを生み出します。

相談相手がいないという孤独
施設で働いていた頃、私は何か判断に迷うことがあれば、すぐに隣にいる先輩や同僚に「これってどう思いますか?」と相談できました。
しかし、訪問介護の現場では、それができません。
利用者さんの容態に変化があった時、予期せぬトラブルが発生した時、その場で判断を下し、対処しなければならないのは自分一人です。
もちろん、事業所に電話すればサービス提供責任者(サ責)が指示をくれますが、その場にいない相手に口頭で状況を正確に伝えるのは、存外難しいものです。
この「すぐに相談できない」という状況が、じわじわと精神的な負担としてのしかかってきます。
「自分の判断は正しかったのか…」
サービスを終えて一人、自転車をこぎながらそんな風に思い悩む時間は、経験した人でなければ分からない、特有のきつさがあります。
全ての責任を一人で負うプレッシャー
一人でサービスを行うということは、その結果に対する責任も一人で負うということです。
転倒させてしまったらどうしよう。
薬の飲ませ間違いをしたらどうしよう。
常にこうしたリスクと隣り合わせでケアを行うプレッシャーは、非常に大きいものがあります。
特に経験の浅いヘルパーにとっては、このプレッシャーが「自分には向いていないのかもしれない」という気持ちに直結しやすいのです。
チームでケアを行い、責任も分散される施設介護とは、この点が根本的に異なります。
訪問介護を辞めたいと感じる人の多くが、この精神的なきつさを理由に挙げるのは、当然のことと言えるでしょう。
訪問介護の仕事が「覚えられない」と感じる背景にある教育体制の問題点
「何度教えてもらっても、訪問介護の仕事が覚えられない…」
もしあなたがそう感じているなら、それはあなたの能力だけの問題ではないかもしれません。
実は、訪問介護事業所の教育体制には、構造的な課題を抱えているケースが少なくないのです。

「見て覚えろ」OJT頼りの研修
多くの事業所では、OJT(On-the-Job Training)が研修の基本となります。
先輩ヘルパーに同行して、実際のサービス提供の様子を見ながら仕事を覚えていくスタイルです。
これ自体は悪いことではありませんが、問題はOJTの「質」です。
十分な研修プログラムがなく、単に「先輩のやり方を見て覚えろ」という丸投げ状態になっている事業所も残念ながら存在します。
教える側の先輩ヘルパーも、自身のスキルや経験則で指導するため、人によって言うことが違う、という事態も起こりがちです。
これでは、新人は混乱するばかりで、一貫した知識や技術を身につけることができません。
マニュアルが整備されていない現実
私が以前勤めていた訪問介護事業所では、利用者さん一人ひとりのケアプランや手順書がきちんとファイルで管理されていました。
しかし、別の事業所では、そうしたマニュアル類がほとんど整備されておらず、サ責からの口頭での指示や、ヘルパー間の申し送りのメモ書きが頼り、という状況でした。
これでは、サービスの質が標準化されず、新人ヘルパーは何を基準に動けばいいのか分かりません。
訪問介護の仕事が覚えられないと感じる背景には、こうした事業所側の教育体制や仕組みの不備が大きく影響しているのです。
もしあなたが今の職場で「覚えられない」と悩んでいるなら、一度、事業所の研修体制やマニュアルの整備状況を客観的に見直してみる必要があるかもしれません。
なぜ介護職は、入職後3ヶ月で辞めることが多いのか?
介護業界では、なぜか入職後3ヶ月で辞める人が多い、という話を耳にしたことはないでしょうか。
これは単なるジンクスではなく、明確な理由があります。
特に訪問介護のような精神的な負担が大きい職場では、この傾向が顕著に現れることがあります。
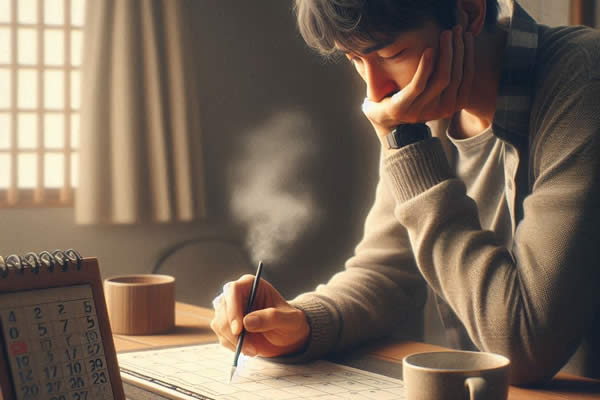
「試用期間」という心理的な節目
多くの会社では、入社後3ヶ月間を「試用期間」として設定しています。
これは働く側にとっても、「この期間で仕事が合うかどうかを見極めよう」という心理的な節目になります。
試用期間中に「この仕事は自分には無理そうだ」「職場の雰囲気が合わない」と感じた場合、「試用期間が終わる今なら、まだ辞めやすいかもしれない」という気持ちが働きやすくなるのです。
介護職が試用期間中に退職したいと思うのは、決して珍しいことではないのです。
「新人」でいられなくなるプレッシャー
入社して1〜2ヶ月は、周りも「新人さんだから」と大目に見てくれることが多いでしょう。
しかし、3ヶ月も経つと、徐々に「一人前のスタッフ」として扱われるようになります。
一人で担当する件数が増えたり、より対応が難しい利用者さんを任されたりと、責任やプレッシャーが増してきます。
このタイミングで、仕事のきつさが一気に増したと感じ、「もう限界だ」と離職を決意するケースは非常に多いのです。
介護職を3ヶ月で辞めるという決断の裏には、こうした環境の変化と心理的なプレッシャーの増大が隠されています。
利用者やサービス提供責任者との人間関係。見えにくい事業所の実態
介護の仕事の悩みとして、常に上位に挙がるのが「人間関係」です。
訪問介護は一人で動くことが多いと思われがちですが、実はここにも特有の人間関係の難しさがあります。
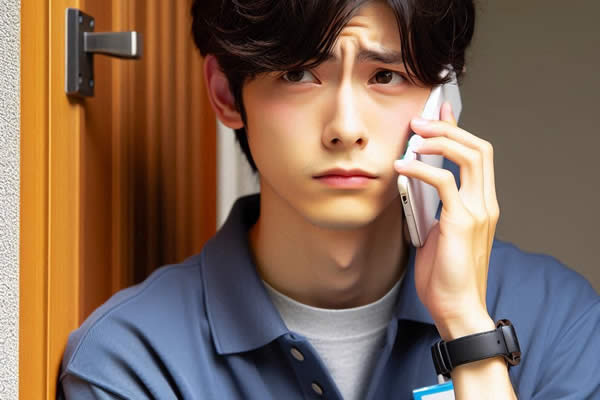
利用者・家族との「相性」という壁
施設介護であれば、多くの利用者さんの中の一人として関わるため、多少相性が合わない方がいても、他のスタッフと協力したり、関わり方を工夫したりする余地があります。
しかし、訪問介護は基本的に1対1の密な関係です。
利用者さんやそのご家族とどうしても相性が合わない場合、その1時間のサービスが非常に苦痛なものになってしまいます。
いわゆる「当たり外れ」と言ってしまうのは不謹慎かもしれませんが、人間同士ですから、どうしても相性の問題は発生します。
この「逃げ場のない関係性」に疲弊し、辞めたいと感じる人は少なくありません。
サ責や同僚との見えにくい関係
訪問介護では、ヘルパーは日中ほとんど外に出ているため、事業所で他のスタッフと顔を合わせる機会は限られます。
そのため、職場の人間関係が見えにくいという特徴があります。
特に重要なのが、サービス提供責任者(サ責)との関係です。
サ責は、ヘルパーのシフトを組み、指示を出し、トラブル対応の窓口となる、いわば司令塔のような存在です。
このサ責が高圧的であったり、相談しにくい人であったりすると、ヘルパーは孤立感を深め、精神的に追い詰められてしまいます。
また、ヘルパー同士の連携がうまく取れていない事業所では、情報の共有がなされず、利用者宅でトラブルに巻き込まれることもあります。
こうした見えにくい人間関係の問題が、じわじわと働きにくさに繋がり、離職の原因となるのです。
「訪問介護をすぐ辞める」と決断する前に。後悔しないための判断基準
ここまで、訪問介護をすぐに辞めてしまう原因について見てきました。
共感できる部分も多かったのではないでしょうか。
では、「辞めたい」という気持ちを抱えたまま、どうすればいいのでしょうか。
感情的に「もう無理だ!」と辞表を叩きつける前に、一度立ち止まって冷静に考える時間を持つことが、後悔しないための第一歩です。
ここでは、あなたの未来のために、今考えるべき具体的な判断基準と、行動の選択肢を提示します。

それでも「訪問介護を辞めたい」なら。就職して2ヶ月目でも可能な円満退職の進め方
色々と考えてみた結果、やはり「辞める」という決意が固まったとします。
たとえ就職して2ヶ月目であっても、円満に退職することは可能です。
社会人としてのマナーを守り、スマートに次へ進むための手順を知っておきましょう。
退職の意思は誰に、いつ伝えるべきか?
まず、退職の意思を最初に伝える相手は、直属の上司です。
訪問介護事業所であれば、サービス提供責任者(サ責)か、事業所の管理者になるでしょう。
同僚に先に話してしまうと、噂が先行してしまい、話がこじれる原因になります。
伝えるタイミングは、法律上は退職日の2週間前で問題ありませんが、会社の就業規則で「1ヶ月前まで」などと定められていることがほとんどです。
円満退職を目指すなら、就業規則に従い、できるだけ早く伝えるのがマナーです。
退職理由の伝え方のコツ
介護職員が就職して2ヶ月目に円満退職するための理由を伝える際には、少しコツが必要です。
たとえ本当の理由が「人間関係が最悪だから」「サ責の指示がめちゃくちゃだから」だったとしても、それをストレートに伝えるのは得策ではありません。
不満をぶつけると、感情的なしこりを残すだけです。
おすすめは、「やむを得ない個人的な事情」として、ポジティブな理由に変換することです。
例えば、以下のような伝え方が考えられます。
- 「実際に働かせていただき、施設介護のようなチームで動く働き方のほうが、より自分の力を発揮できると強く感じました。大変申し訳ありませんが、改めて施設介護の道に進みたいと考えております」
- 「家族の事情(体調など)で、現在の働き方を続けることが難しくなりました。ご迷惑をおかけして申し訳ありません」
あくまで「事業所のせい」ではなく、「自分の都合」という形にすることで、相手も引き止めにくくなり、スムーズに話が進みやすくなります。
訪問介護で「辞めたいけど辞めさせてくれない」時の具体的な対処法
あってはならないことですが、人手不足などを理由に、事業所がなかなか辞めさせてくれないケースもあります。
「代わりの人が見つかるまで待ってくれ」
「今辞められたら困る」
こうした言葉で引き止められ、あなたが訪問介護を辞めたいのに辞めさせてくれない状況に陥ってしまったら、どうすればいいのでしょうか。

まずは法律という「最強の武器」を知る
大前提として、労働者には「退職の自由」が法律で保障されています。
民法第627条では、期間の定めのない雇用契約の場合、労働者はいつでも解約の申し入れをすることができ、申し入れの日から2週間が経過すれば雇用は終了すると定められています。
つまり、あなたが「辞めます」と伝えてから2週間が経てば、会社が何と言おうと、あなたは法的に辞めることができるのです。
これは非常に強力な権利であり、あなたの「お守り」になります。
話し合いで解決しない場合の最終手段
まずは上司と冷静に話し合うのが基本ですが、それでも「辞めさせない」という態度を崩さない場合は、次のステップに進みます。
それは、「退職届」を内容証明郵便で送付するという方法です。
内容証明郵便は、「いつ、誰が、誰に、どんな内容の文書を送ったか」を郵便局が証明してくれるサービスです。
これにより、「退職の意思表示をした」という動かぬ証拠が残ります。
退職届が会社に届いた日から2週間後が、あなたの正式な退職日となります。
ここまで来ると、会社側もごね得はできないと理解せざるを得ません。
訪問介護の現場で辞めたいのに辞めさせてくれないという最悪の事態に備え、こうした知識を持っておくことは、自分自身を守るために非常に重要です。
あなたは本当に「向いていない」?仕事を続けるかどうかの見極めポイント
「もう辞めたい」という気持ちが強いと、「自分は訪問介護に向いていないんだ」と短絡的に結論づけてしまいがちです。
しかし、本当にそうでしょうか?
辞めるという決断を下す前に、一度冷静に自己分析をしてみることをお勧めします。
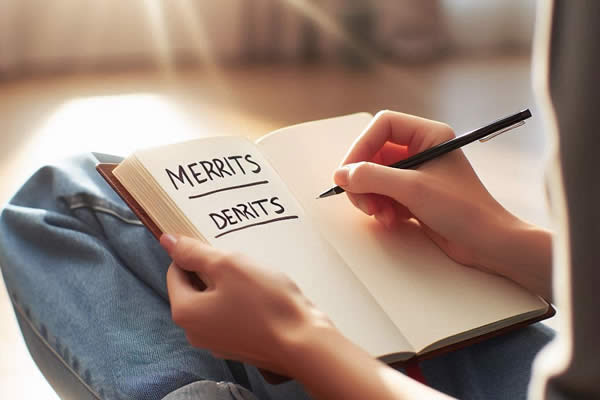
「仕事」が嫌なのか、「職場」が嫌なのか?
まず、あなたにとっての「嫌だ」という感情が、どこから来ているのかを切り分けて考えてみましょう。
- 「仕事」が嫌:利用者さんと1対1で関わること自体が苦痛、介護という業務そのものが合わない、など。
- 「職場」が嫌:今の事業所の人間関係が悪い、教育体制が不十分、給与や待遇に不満がある、など。
もし後者の「職場」が原因なのであれば、あなたは訪問介護に「向いていない」わけではありません。
職場を変えることで、問題が解決する可能性が大いにあります。
私自身、複数の職場を経験してきましたが、同じ訪問介護事業所でも、所長の理念やサ責の人柄によって、働きやすさは天と地ほども違いました。
「訪問介護」という仕事全体を嫌いになる前に、今の「職場」に問題がないか、客観的に評価してみてください。
続けるメリットとデメリットを書き出してみる
頭の中だけで考えていると、堂々巡りになりがちです。
そんな時は、紙とペンを用意して、シンプルに「今の仕事を続けるメリット・デメリット」を書き出してみましょう。
- メリット:安定した給料、知っている利用者さんがいる安心感、通勤が楽、など
- デメリット:精神的にきつい、休みが取りにくい、スキルアップが見込めない、など
書き出してみることで、自分の考えが整理され、どちらの選択肢が自分にとって重要なのかが、視覚的に見えてきます。
介護職が突然辞めるのはNG?1日で辞めた場合などのリスクを解説
精神的に追い詰められると、「もう明日から行きたくない」「バックレてしまいたい」という衝動に駆られることもあるかもしれません。
しかし、介護職が突然辞めるという行為は、あなた自身にとって多くのリスクを伴います。
たとえ介護職を1日で辞めたくなったとしても、正規の手続きを踏むことが重要です。

「バックレ」がもたらす現実的な不利益
連絡もせずに仕事を辞めてしまう、いわゆる「バックレ」行為は、絶対に避けるべきです。
まず、給与が正常に支払われない可能性があります。
また、転職活動に必要な離職票や源泉徴収票などの書類を発行してもらえず、次のステップに進む上で大きな支障となります。
失業保険の手続きもできなくなるかもしれません。
一時的な感情で行動した結果、あなた自身が経済的・手続き的な不利益を被ることになるのです。
狭い介護業界での評判リスク
介護業界は、あなたが思っている以上に狭い世界です。
地域の事業所同士で情報交換をしていることも少なくありません。
「あの事業所をバックレた人」という不名誉な評判は、案外すぐに広まってしまう可能性があります。
そうなれば、今後の転職活動で不利に働くことは言うまでもありません。
どんなに辛くても、社会人としての最低限の筋道は通し、正規の手続きを踏んで退職することが、あなた自身の未来を守ることに繋がるのです。
辞めた後の選択肢は?働きやすい事業所の見つけ方とおすすめの転職先
もし、あなたが「今の職場は辞める。でも、訪問介護の仕事自体は続けたい」あるいは「介護の経験を活かして別の働き方をしたい」と考えているなら、未来は明るいです。
選択肢は一つではありません。

訪問介護を続けるなら、良い事業所の見極めがカギ
「職場が合わなかっただけ」と結論が出たなら、次は失敗しない事業所選びが重要です。
面接の際には、こちらからも積極的に質問をしましょう。
- 「研修制度はどのようになっていますか?OJT以外に座学の研修はありますか?」
- 「ヘルパーさんが月に何回くらい集まる機会がありますか?」
- 「サ責の方は何名いらっしゃいますか?緊急時の連絡体制はどうなっていますか?」
こうした質問に対する答え方で、その事業所がスタッフを大切にしているか、教育体制が整っているかがある程度見えてきます。
見学をさせてもらい、事業所の雰囲気やスタッフの表情を見てみるのも非常に有効です。
施設介護や別の職種へ。経験を活かすキャリアチェンジ
訪問介護の経験は、決して無駄にはなりません。
1対1で利用者と向き合い、その人の生活全体をアセスメントした経験は、他の介護現場でも必ず活かせます。
- 施設介護(特養、有料、サ高住など):チームで働く安心感を得たいなら、施設介護に戻るのも良い選択です。訪問介護で培ったコミュニケーション能力は、利用者やその家族との関係構築に大いに役立つでしょう。
- デイサービス:レクリエーションなどが好きな方には、デイサービスの職員もおすすめです。
- 介護の経験を活かせる異業種:例えば、福祉用具専門相談員や、介護用品を扱う企業の営業職など、介護の知識を活かせるフィールドは他にも広がっています。
私自身も、現場を離れて事務職という立場から介護に関わっています。
一つの働き方に固執せず、広い視野であなたの次のキャリアを考えてみてください。
まずは、ハローワークインターネットサービスのような公的なサイトで、どのような求人があるのかを幅広く情報収集してみることから始めるのも良いでしょう。
あなたの経験を求めている職場は、きっと見つかります。
まとめ:訪問介護をすぐ辞める人が多い理由と、あなたのこれから
今回は、「なぜ訪問介護はすぐ辞める人が多いのか」というテーマで、その原因と、辞めたいと思った時の判断基準についてお話ししてきました。
この記事のポイントを、最後にもう一度整理しておきましょう。
- 訪問介護の早期離職の原因は、理想と現実のギャップ、一人で働くことによる精神的負担、教育体制の不備、人間関係など、構造的な問題が多い。
- 辞めるか続けるか判断する際は、「仕事」が嫌なのか「職場」が嫌なのかを冷静に切り分けることが重要。
- 退職を決意したなら、たとえ短期であっても円満退職を目指すのが社会人としてのマナー。
- どうしても辞めさせてくれない場合は、法律という武器があることを知っておくこと。
- あなたの経験は無駄にはならない。訪問介護以外の施設や職種にも、活躍の場は広がっている。
「もう辞めたい」と感じている時、視野はどうしても狭くなりがちです。
しかし、どうか「自分はダメな人間だ」と責めないでください。
あなたが今感じている辛さは、決してあなた一人のせいではありません。
この記事が、あなたの心を少しでも軽くし、後悔のない選択をするための一助となれたなら、これほど嬉しいことはありません。
あなたの未来が、よりあなたらしく輝ける場所へと繋がっていることを、心から願っています。




コメント