介護職の先輩が怖い…。
指導の範疇を超えた理不尽な態度や、無視、きつい言い方に、心がすり減っていませんか。
「もう辞めたい…」と毎日のように感じているかもしれません。
その気持ち、10年以上この業界で渡り鳥のように様々な施設を経験してきた私には、痛いほどよく分かります。
しかし、その感情だけで職場を去ってしまうのは、あまりにもったいない。

この記事では、なぜ介護の現場で「怖い先輩」が生まれやすいのか、その背景にある理由を冷静に分析します。
その上で、あなたが明日からすぐに実践できる、心をすり減らさないための具体的な対処法を7つ、私の経験を交えながら詳しくお伝えします。
この記事を読み終える頃には、あなたの心は少し軽くなり、今の状況を乗り越えるための具体的な武器を手に入れているはずです。
なぜ介護職の先輩は怖いのか?元職員が考える5つの理由
「怖い」と感じるのには、必ず理由があります。
そして多くの場合、その原因はあなた一人にあるわけではありません。
私自身、特養、有料老人ホーム、訪問介護と様々な現場を経験してきましたが、程度の差こそあれ、新人が委縮してしまうような先輩はどこの職場にも存在しました。
まずは相手を理解するために、そして何よりあなた自身が「自分のせいだ」と追い詰められないために、その背景にある構造的な問題を冷静に見ていきましょう。

【怖い先輩あるある】言い方がきつい、無視するなど具体例
あなたも、こんな経験はありませんか?
これは、私が現場で見聞きしてきた「怖い先輩」の典型的な行動パターンです。
- 申し送りの場で、自分にだけ質問のトーンが明らかに違う。
- 挨拶をしても、聞こえないふりをするか、ため息をつかれる。
- 些細なミスを、他の職員もいる前で大声で執拗に責める。
- 分からないことを質問しに行くと、「そんなことも知らないの?」と見下した態度をとる。
- その先輩独自の「ローカルルール」を教えられておらず、後から「なんでやってないの?」と怒られる。
- ナースコールに自分が出ると、あからさまに嫌な顔をする。
一つでも当てはまれば、あなたが「怖い」と感じるのは当然のことです。
これらは指導ではなく、単なる感情的な八つ当たりや、いじわるである可能性が高いと言えます。
まずは「自分が弱いからだ」ではなく、「これは誰が経験しても怖いと感じる状況なのだ」と認識することが大切です。
介護現場の慢性的な人手不足とストレスが生む負の連鎖
なぜ、このような行動をとる先輩が生まれてしまうのでしょうか。
最大の原因の一つは、介護業界全体の構造的な問題である「人手不足」にあります。
私が事務職員として現場の勤怠管理やシフト作成に携わるようになった今、この問題の根深さを改めて痛感しています。

常にギリギリの人数で現場を回している施設は少なくありません。
一人でも欠員が出れば、残された職員の負担は一気に増大します。
このような状況では、職員は常に時間に追われ、心身ともに余裕がなくなっていきます。
十分な休息が取れず、疲労とストレスが蓄積した結果、感情のコントロールが難しくなり、その矛先が最も立場の弱い新人職員に向かってしまうのです。
これは、怖い先輩個人の資質だけの問題ではなく、過酷な労働環境が生み出した、ある種の「負の連鎖」と言えるかもしれません。
「自分のやり方が絶対」旧態依然とした指導法と価値観の押し付け
介護の世界は、良くも悪くも経験が重視される傾向にあります。
長年同じ施設で働いている先輩の中には、残念ながら「自分のやり方こそが、この施設の絶対的なルールだ」と勘違いしてしまっている方がいます。

私が有料老人ホームから特別養護老人ホームへ転職した際、移乗介助の方法の違いに戸惑ったことがありました。
前の施設で安全だと教わった方法を実践したところ、ある先輩から「うちはそのやり方じゃないから」と、問答無用で否定された経験があります。
もちろん、施設ごとに理念や方針があり、ケアの方法が異なるのは当然です。
しかし、なぜその方法なのかという根拠を説明せずに、ただ自分のやり方を押し付けるのは、適切な指導とは言えません。
特に、新しい知識や技術を学ぶ意欲がなく、過去の成功体験だけに固執している先輩ほど、自分のやり方を否定されることを極端に嫌います。
そして、新しいやり方を持ち込む新人や中途職員を「和を乱す存在」と見なし、攻撃的になることがあるのです。
実は自信のなさの表れ?マウントを取ることで自分を保つ心理
一見、威圧的に見える怖い先輩ですが、その態度の裏には、実は強い劣等感や自信のなさが隠れているケースが少なくありません。
例えば、異業種から転職してきたあなたが、前の職場で培ったコミュニケーション能力を発揮して、すぐに利用者さんと打ち解けたとします。

それを見た先輩が、自分の居場所が脅かされるような、あるいは自分の存在価値が揺らぐような、無意識の不安や嫉妬を感じることがあるのです。
その不安を打ち消すために、あなたに対して「介護の基本がなっていない」などと、わざと優位に立てるポイントを探してマウントを取り、自分のプライドを保とうとします。
つまり、あなたを攻撃することでしか、自分の心の安定を保てないのです。
そう考えると、少しだけ相手を客観的に見られるようにならないでしょうか。
「ああ、この人は今、自分の心のバランスを取るのに必死なんだな」と思えれば、理不尽な言葉を真正面から受け止めて傷つく必要はない、と気づけるはずです。
中には「介護の仕事があほらしい」と感じている、やる気ない職員もいる現実
残念なことですが、これもまた現実です。
全ての介護職員が、高い志ややりがいを持って働いているわけではありません。
中には、生活のために仕方なく、あるいは他に選択肢がなかったからという理由で働いている人もいます。

そうしたやる気ない職員にとって、情熱を持って仕事に取り組もうとする新人の存在は、時に目障りですらあります。
自分がとうに失ってしまった輝きを、まざまざと見せつけられるようで不快に感じるのです。
また、仕事へのモチベーションが低いため、新人指導を「面倒な仕事が増えた」としか捉えられず、雑な対応になったり、ストレスのはけ口にしたりします。
私が以前いた施設にも、「どうせ給料は同じなんだから、適当でいいんだよ」が口癖の先輩がいました。
そうした職員が「介護の仕事なんてあほらしい」と口にするのを聞くと、真面目に取り組んでいるこちらのやる気まで削がれてしまいます。
もしあなたの怖い先輩がこのタイプなら、関わるだけ時間の無駄かもしれません。
これはもう、あなたにはどうすることもできない問題です。
介護職の先輩が怖い…心をすり減らさない具体的対処法7選
怖い先輩が生まれる背景が分かったとしても、今まさにあなたが直面している辛さが消えるわけではありません。
ここからは、あなたがこれ以上心をすり減らすことなく、現状を乗り越えるための具体的な対処法を7つ、ご紹介します。
どれも私が実際に試したり、同僚たちが実践したりして効果があったものです。
できそうなものから、一つでもいいので試してみてください。

①「これは相手の課題」と割り切る思考法で心を守る
まず、最も大切な心構えです。
それは、「相手の機嫌は、相手の課題であって、自分の課題ではない」と割り切ること。
先輩がイライラしているのは、人手不足のせいかもしれませんし、プライベートで何か嫌なことがあったのかもしれません。
その原因は、あなたにはコントロール不可能です。
それなのに、あなたが「私のせいで機嫌が悪いんだ…」と思い悩むのは、他人の荷物まで背負ってしまっているのと同じです。
理不尽に怒られた時は、心の中でこう呟いてみてください。
「お疲れ様です。何か大変なことがあるんですね。でも、それはあなたの問題です」
相手の感情の波に、あなたまで飲み込まれる必要は一切ありません。
物理的に距離を取るのが難しくても、心の中に一本の線を引く。
この思考法は、あらゆる人間関係のストレスからあなたを守ってくれる強力な盾になります。
②理不尽な言動は記録する。お守り代わりになる「客観的メモ」のすすめ
「そんなことで悩むなんて、考えすぎだよ」
もしあなたが誰かに相談した時、このように言われてしまったら、さらに深く傷ついてしまいますよね。
そうならないためにも、「事実」を記録しておくことを強くお勧めします。

これは、誰かを訴えるためや、仕返しをするためではありません。
第一の目的は、あなた自身の心を守るためです。
スマホのメモ帳や小さなノートで構いません。
以下の項目を、感情を交えずに淡々と記録してみてください。
- いつ(年月日、時間)
- どこで(スタッフルーム、廊下など)
- 誰に(先輩の名前)
- 何を言われたか/されたか(具体的な言動をそのまま)
- 他に誰がいたか(目撃者)
これを続けると、「自分はこんなに理不尽な扱いを受けていたんだ」という事実が可視化され、「自分が悪いわけじゃない」と客観的に認識できます。
そしてこの記録は、万が一、上司やさらに上の立場の人に相談する必要が出てきた時に、感情論ではない「事実」を伝えるための強力な武器、そして何よりあなたの心の「お守り」になります。
③一人で抱えない。信頼できる同僚や上司に相談する勇気
一人で抱え込むのは、最も危険な状態です。
辛い気持ちを吐き出すだけでも、心は少し軽くなります。
大切なのは、相談する相手を慎重に選ぶことです。

誰にでも話せばいい、というわけではありません。
理想的な相談相手は、
- 口が堅く、客観的な視点を持っている人
- あなたの話を否定せずに最後まで聴いてくれる人
です。
まずは、一番話しやすい同期や、年齢の近い先輩に「ちょっと聞いてもらえませんか?」と声をかけてみてはいかがでしょうか。
「実は〇〇先輩のことで少し悩んでいて…」と切り出せば、案外「私も同じことを感じてた!」と共感してくれるかもしれません。
味方が一人いると分かるだけで、精神的な支えになります。
もし、ユニットリーダーやフロア長など、役職のある上司の中に信頼できそうな人がいれば、勇気を出して相談するのも一つの手です。
その際は、②で作成した「客観的メモ」を使い、感情的にならずに事実を伝えることが重要です。
④介護職の新人イビリ?と感じたら、感情的にならず事実を報告する
相談しても状況が改善しない、あるいは明らかに業務に支障が出ている場合、それはもう「指導」の範囲を超えた「新人イビリ」やパワーハラスメントの可能性があります。
この段階になったら、「相談」から「報告」へとステップを上げる必要があります。

報告する相手は、フロア長や施設長、あるいは本社の人事部など、その先輩よりも上の立場にある、問題を解決する権限を持った人です。
ここでも重要なのは、感情的にならないこと。
「ひどいイジメを受けています!」と訴えるのではなく、あくまで「業務上の報告・確認」というスタンスで伝えます。
例えば、
「〇〇先輩から、『このやり方は間違っている』とご指導いただいたのですが、マニュアルを確認したところ、私の手順に誤りはないように思われます。施設の統一した手順として、どちらが正しいのか、ご確認いただけますでしょうか」
というように、②のメモに基づいた事実を伝え、判断を仰ぐ形を取るのです。
こうすることで、あなたはただの被害者ではなく、職場の問題を改善しようとする主体的な職員として映ります。
これは、あなた自身を守ると同時に、職場全体の環境改善にも繋がる可能性を秘めた行動です。
もし、直属の上司や施設長に報告しても改善が見られない場合や、そもそも社内の人には相談しづらいという状況であれば、外部の公的な相談窓口を利用することも考えてみてください。
全国の労働局や労働基準監督署内には、職場のトラブルに関する相談を無料で受け付けてくれる「総合労働相談コーナー」が設置されています。
専門の相談員が、パワハラの問題も含めて、法的な観点からどうすべきかアドバイスをくれます。
匿名での相談も可能なので、一人で抱え込まず、客観的な意見を聞いてみるのも大切なことです。
⑤介護職のいじめに仕返しはダメ。自分の未来を大切にする考え方
理不尽な扱いを受け続ければ、「いつか見返してやりたい」「同じ思いをさせてやりたい」という気持ちが芽生えるのも無理はありません。
私も若い頃、あまりに意地悪な先輩のロッカーにこっそり…と考えたことが一度や二度ではありませんでした。

しかし、断言します。
仕返しは、絶対にダメです。
なぜなら、仕返しをした瞬間、あなたも相手と同じレベルに落ちてしまうからです。
そして、万が一その行為が明るみに出れば、あなたの立場は一気に悪くなります。
「あいつも問題のある職員だ」というレッテルを貼られ、せっかく味方になってくれそうだった人たちも離れていってしまうでしょう。
悔しい気持ちを向けるべきは、相手への復讐ではありません。
そのエネルギーは、あなた自身の未来のために使うべきです。
悔しさをバネに仕事のスキルを磨く、資格の勉強を始める、あるいはもっと良い環境を探すために使う。
あなたの貴重な時間とエネルギーを、くだらない相手のために浪費してはいけません。
⑥仕事の知識や技術を磨き、むかつく職員に何も言わせない実力をつける
これは、最も建設的で、長期的にあなたを助けてくれる対処法です。
怖い先輩があなたに攻撃してくる隙は、どこにあるでしょうか。
それは多くの場合、「仕事のミス」や「知識不足」です。
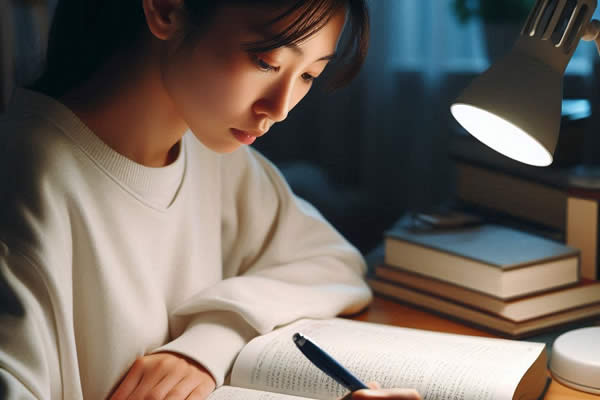
ならば、その攻撃材料を一つずつ潰していけばいいのです。
- 業務マニュアルを隅から隅まで読み込む。
- 分からないことは、怖い先輩ではなく、他の親切な先輩に積極的に質問する。
- 介護技術に関する本を読んだり、研修に参加したりする。
- 介護福祉士などの資格取得を目指して勉強を始める。
最初は大変かもしれません。
しかし、知識と技術が身につくにつれて、あなたは自信を持って仕事に取り組めるようになります。
そして、「あの人に任せておけば大丈夫」「新人だけど、よく知っている」という信頼が周囲から得られるようになれば、理不尽な攻撃は自然と減っていきます。
何より、実力をつけることは、あなた自身の市場価値を高めることに直結します。
この先、万が一転職することになったとしても、その知識とスキルはあなたを裏切らない、一生の財産になるのです。
⑦最終手段は「戦略的撤退」。心身が限界になる前に転職を検討する
これまで6つの対処法をお伝えしてきましたが、それでも状況が改善しない、あるいは、もうすでに心身に不調が出始めているのなら、ためらわずに「撤退」を選んでください。
これは「逃げ」ではありません。
あなたの心と体を守り、あなたの未来の可能性を潰さないための、賢明な「戦略的撤退」です。

私が事務職として様々な職員の入退職を見てきて思うのは、「一つの職場が全てではない」ということです。
世の中には、驚くほどたくさんの介護施設があり、その数だけ異なる文化や人間関係があります。
職員同士が協力し合い、新人を大切に育てようという風土の職場も、間違いなく存在します。
あなたの心が壊れてしまう前に、動くことが何よりも大切です。
「もう少し頑張れば…」という考えは危険です。
限界を超えてしまうと、気力がなくなり、転職活動をするエネルギーさえ残っていなくなってしまいます。
今の職場が、あなたの貴重な介護キャリアの全てではありません。
あなたの頑張りを正当に評価し、あなたらしく働ける場所は、必ずどこかにあります。
自分を責めず、どうかその可能性を信じてください。
まとめ:介護職の先輩が怖いと感じたあなたへ
今回は、介護職の先輩が怖いと感じる理由と、具体的な対処法について詳しく解説しました。
先輩が怖いのは、決してあなた一人のせいではありません。
人手不足やストレス、旧態依然とした指導法など、様々な背景が複雑に絡み合っているケースがほとんどです。
大切なのは、その事実を理解し、一人で抱え込まないこと。
そして、理不尽な言動を記録したり、信頼できる人に相談したり、仕事のスキルを磨いて自信をつけたりと、あなた自身を守るための具体的な行動を起こすことです。
それでもどうしても状況が改善せず、心身が限界だと感じたなら、そこから離れる「戦略的撤退」も、あなたの未来を守るための立派な選択肢の一つです。
あなたの介護人生は、一人の怖い先輩によって左右されるべきものではありません。
この記事が、あなたが自分らしく働くための一歩を踏み出す、小さなきっかけになることを心から願っています。




コメント