介護の仕事で、利用者さんから思いがけず厳しい言葉を投げかけられ、深く落ち込んでしまう。
真面目に仕事に取り組んでいる方ほど、「自分の対応が悪かったのだろうか…」とご自身を責めてしまうことは少なくありません。
お気持ち、痛いほど分かります。
私も現場にいた頃は、理不尽な言葉に心をすり減らす毎日でした。

しかし、その怒りの原因は、必ずしもあなたにあるわけではないのです。
この記事では、10年以上様々な介護現場を渡り歩いた私が、利用者に怒られても心を壊さずに「気にしない」ための具体的な思考術を7つ、徹底的に解説します。
この記事を読み終える頃には、あなたの心は少し軽くなり、明日からの仕事に前向きな気持ちで臨めるようになっているはずです。
- 介護で利用者に怒られるのはなぜ?あなたが悪いわけではない主な原因
- 利用者に怒られても気にしない!介護職が心を壊さない実践的思考術7選
介護で利用者に怒られるのはなぜ?あなたが悪いわけではない主な原因
介護の現場で利用者さんから怒られてしまうと、どうしても「自分のせいだ」と感じてしまいがちです。
しかし、一度立ち止まって、その背景を冷静に考えてみることが大切です。
実は、その怒りの根本的な原因は、あなたの対応とは別のところにあるケースが非常に多いのです。
ここではまず、なぜ利用者は怒ることがあるのか、その主な原因を私の経験も交えながら掘り下げていきます。
この原因を知るだけでも、あなたの心の負担はかなり軽くなるはずです。

原因①:認知症の症状や病気からくる不安・混乱
まず理解しておくべき最も大きな原因は、認知症という病気の症状です。
特に、暴言や感情の起伏が激しくなるといった症状(BPSD:行動・心理症状)は、ご本人の意思とは関係なく現れることがあります。
脳の機能低下が引き起こす世界
認知症になると、記憶が曖昧になったり、今いる場所や時間が分からなくなったりします(見当識障害)。
考えてみてください。
もし自分が誰なのか、ここがどこなのか、目の前にいる人が誰なのか分からない状況に置かれたら、とてつもない不安と混乱に襲われるはずです。
その不安が、身近にいる介護職員への攻撃的な言動として現れてしまうのです。
「財布を盗んだ!」「家に帰らせろ!」といった言葉は、あなた個人を非難しているわけではありません。
それは、ご本人が見ている「不安な世界」から発せられている、助けを求める叫びのようなものなのです。
原因②:「偉そう」「わがまま」に見える言動の裏にある心理とは?
中には、認知症の症状とは少し違う、一見すると「偉そう」だったり「わがまま」に感じられたりする言動に悩まされることもあるでしょう。
「私の若い頃はこうだった」「もっと丁寧にやれ」といった言葉に、心が折れそうになる気持ちも分かります。
しかし、そうした言動の裏にも、加齢に伴う複雑な心理が隠されています。
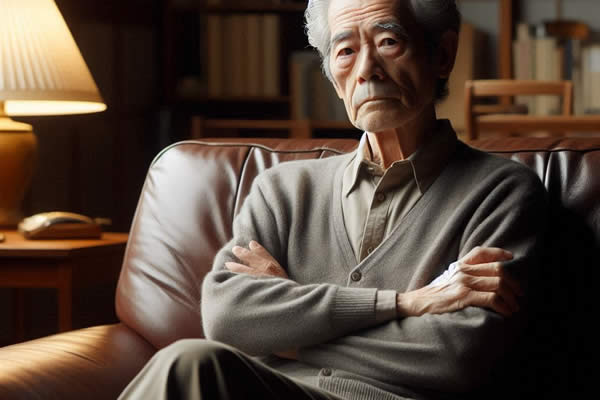
失われていくものへの抵抗とプライド
年を重ねるということは、これまで当たり前にできていたことが一つ、また一つとできなくなっていく「喪失の連続」でもあります。
誰かの助けを借りなければ生活がままならなくなる状況は、ご本人のプライドを深く傷つけます。
その失われた自信を取り戻そうとする防衛反応が、時に介護者に対して「偉そう」な態度として現れるのです。
また、身体のどこかに常に痛みや不快感を抱えていることも少なくありません。
その不快感をうまく言葉で表現できず、不機嫌さや攻撃的な態度で示してしまうケースもよく見られます。
一見わがままに見える要求も、実は「もっと自分に関心を持ってほしい」「不安な気持ちを分かってほしい」という、承認欲求の表れなのかもしれません。
原因③:職員の多忙さや職場環境が引き起こす悪循環
利用者さんの怒りの原因は、ご本人側の要因だけではありません。
私たち介護職員側の状況、特に「忙しさ」が、知らず知らずのうちに利用者さんを追い詰めている可能性も考えなければなりません。
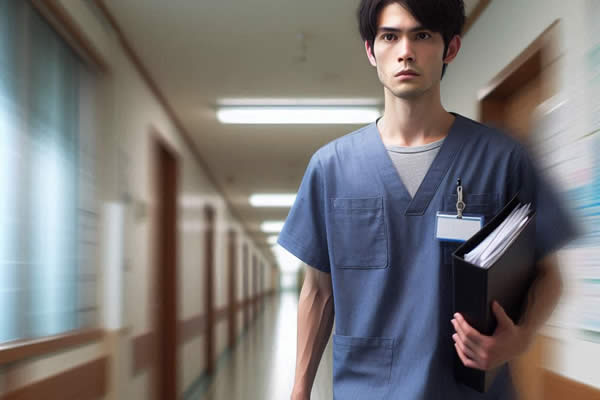
忙しさが作る「見えない壁」
人手不足の現場では、どうしても一人ひとりの業務に追われ、効率が最優先されがちです。
職員が常にバタバタと走り回っているような環境では、利用者さんは「何か頼んだら悪いな」「忙しそうだから後にしよう」と遠慮してしまいます。
そして、我慢が限界に達した時に、些細なことをきっかけに溜め込んだ不満が爆発してしまうのです。
これは、誰か一人が悪いというよりは、職場全体の体制や雰囲気の問題です。
私が事務職として現場を見ていると、職員の余裕のなさがフロア全体の緊張感を高め、それが利用者さんの不安を煽っていると感じる場面が実際にあります。
利用者さんの怒りは、私たち自身の働き方を見直すきっかけを与えてくれる「鏡」のような役割を果たしているのかもしれません。
原因④:【私の体験談】特養と有料老人ホームで感じた「怒りの質」の違い
私はこれまで、特別養護老人ホーム(特養)から富裕層向けの有料老人ホーム、訪問介護まで、様々な現場を「渡り鳥」のように経験してきました。
その中で気づいたのは、施設の種類によって利用者さんから向けられる「怒りの質」が全く異なるということです。

症状が主体の「特養」と要求が主体の「有料」
例えば、私が働いていた特養では、やはり認知症の症状が原因となっている怒りが大半でした。
それは理屈ではなく、感情のほとばしりのような、ある意味で分かりやすい怒りです。
一方で、有料老人ホームでは、お客様意識が強い方が多く、「お金を払っているのだから、このくらいのサービスは当然だ」という、より論理的(?)な要求やクレームに近い形の怒りに直面することが多くありました。
丁寧な言葉遣いの中に、チクリと棘のある一言を混ぜてくるような、精神的にじわじわと削られるような感覚です。
このように、「怒り」と一括りにせず、その背景にあるものを施設形態や利用者層の特性から分析してみることで、「これは個人の問題ではなく、環境の特性なのだ」と客観的に捉えやすくなります。
原因⑤:ついカッとなって利用者へ暴言…となる前に知っておくべきこと
毎日理不尽な言葉を浴びせられ続ければ、どれだけ冷静を心がけていても、ついカッとなってしまう瞬間はあるかもしれません。
「いい加減にしてください!」と、利用者さんへ暴言を吐いてしまいそうになる自分に気づき、自己嫌悪に陥る方もいるでしょう。

怒りは自然な感情、でも行動は選べる
まず、怒りの感情が湧き上がること自体は、人間としてごく自然な反応です。
自分を責める必要はありません。
大切なのは、その怒りを「どうコントロールし、どう行動に移すか」です。
感情に任せて暴言を吐いてしまえば、それはプロフェッショナルな行為とは言えず、何より自分自身を深く傷つける結果になります。
後のセクションで詳しく解説しますが、怒りの感情のピークは、実は長くて6秒程度と言われています。
カッとなったら、まずはその場を少し離れて深呼吸をする。
この「6秒」をやり過ごす術を知っているだけで、取り返しのつかない事態を避けることができます。
利用者さんへの暴言は、自分自身のキャリアを守るためにも絶対に避けなければならない一線だと心得ておきましょう。
利用者に怒られても気にしない!介護職が心を壊さない実践的思考術7選
利用者さんに怒られる原因が自分だけにあるわけではないと分かっても、やはり実際に厳しい言葉を浴びせられれば落ち込んでしまうものです。
大切なのは、そのダメージを心の中に溜め込まず、上手に受け流していく技術を身につけること。
ここからは、私が現場時代に実践し、今も多くの職員に伝えている「心を壊さないための具体的な思考術」を7つご紹介します。
どれも明日からすぐに試せるものばかりですので、ぜひ参考にしてみてください。

思考術①:「自分」と「役割」を切り離して客観視する
まず最も基本的で強力な思考術が、「本来の自分」と「介護職としての役割を演じている自分」を意識的に切り離すことです。
これは一種のメンタルコントロール術と言えるかもしれません。
心に「介護職」という名の鎧を着る
あなたは、24時間365日「介護職員」である必要はありません。
職場にいる間は、「介護職員」というプロフェッショナルの役割を演じているのだ、と考えてみてください。
利用者さんからの言葉は、あなた個人の人格に向けられたものではなく、その「介護職員」という役割に対して向けられているもの。
そう捉えることで、言葉のナイフが自分の心の奥深くまで突き刺さるのを防ぐことができます。
制服に着替える時に「さあ、介護職のスイッチをオンにしよう」と考え、退勤時に制服を脱ぐ時に「これで役割は終わり。素の自分に戻ろう」と意識するだけでも、気持ちの切り替えがスムーズになります。
思考術②:理不尽な言葉は「心のスルー機能」で受け流す
すべての言葉を真正面から100%受け止めていては、どんなに屈強な精神の持ち主でも疲弊してしまいます。
特に、明らかに理不尽だと感じる言葉に対しては、「心のスルー機能」を最大限に活用しましょう。

脳内実況で言葉を「現象」として捉える
利用者さんが怒り始めたら、心の中で「おっと、〇〇さん、お怒りモードに入りました」「BPSDの波が来たようです」と、まるでスポーツ実況のように客観的に状況を分析してみてください。
少し不謹慎に聞こえるかもしれませんが、これは感情を切り離し、目の前の出来事を「個人的な攻撃」ではなく「対処すべき現象」として捉えるための有効なトレーニングです。
言葉をシャボン玉のようにイメージし、自分の体に触れる前にフッと消えていくのを想像するのも良いでしょう。
自分なりの「受け流し方」のレパートリーをいくつか持っておくと、いざという時に心の余裕が生まれます。
思考術③:利用者からの暴力や暴言には、まず安全確保とクールダウン
言葉だけでなく、時には手が出てしまうような、利用者さんからの暴力的な行為に直面することもあるかもしれません。
このような緊急時には、何よりもまずあなた自身の安全を確保することが最優先です。

逃げるが勝ち、はプロの判断
危険を感じたら、すぐに利用者さんから物理的な距離を取りましょう。
「ここで自分が対応しなければ」という真面目さや責任感が、かえって事態を悪化させることがあります。
まずは冷静になれる安全な場所まで下がり、他の職員に応援を求める。
これは決して「逃げ」ではなく、自分と相手を守るためのプロフェッショナルな判断です。
そして、相手だけでなく、自分自身もクールダウンする時間を確保することが重要です。
興奮状態のままでは、適切な対応はできません。
一度深呼吸をして、落ち着いてから状況を振り返り、チームとしてどう対応するかを検討しましょう。
思考術④:「なぜ利用者に優しくできない?」自分の感情と向き合う大切さ
特定の利用者さんに対して、どうしても優しくできない。
そんな自分に気づき、罪悪感を覚えてしまうこともあるでしょう。
時には、嫌いな利用者さんを無意識に無視してしまうような態度をとってしまうかもしれません。

「優しくできない」自分を許すことから始める
まず受け入れてほしいのは、「優しくできない自分」を責める必要はないということです。
介護職も人間です。
相性もあれば、感情の波もあります。
大切なのは、「なぜ自分はこの人に対して優しくなれないのだろう?」と、自分の感情と正直に向き合ってみることです。
「大声で話すのが苦手だからだ」「過去の嫌な経験を思い出してしまうからだ」など、理由が見えてくると、それは「嫌い」という漠然とした感情ではなく、対処可能な「課題」に変わります。
自分の感情を否定せず、まずは「そう感じているんだな」と認めてあげること。
それが、次のステップに進むための第一歩になります。
思考術⑤:一人で抱えない!「記録」を武器にチームの問題として対応する
利用者さんとの間で起きたトラブルは、決してあなた一人で抱え込むべき問題ではありません。
それは、施設全体で共有し、チームとして解決策を探るべき課題です。
その際に、最も強力な「武器」となるのが客観的な事実に基づいた「記録」です。

介護記録はあなたを守る盾になる
「いつ、どこで、誰が(利用者)、誰に(職員)、何を言ったか/何をしたか、その結果どうなったか」を、感情を交えずに事実だけを淡々と記録に残しましょう。
この客観的な記録があることで、カンファレンスなどの場で具体的な状況を正確に共有でき、チームとして一貫した対応方針を立てることができます。
「〇〇さんからこういう暴言があったので、今後は複数名で対応しましょう」といった具体的な対策に繋がるのです。
また、事務方の視点から補足すると、この記録は万が一の事態が発生した際に、職員が適切な対応をとっていたことを証明する重要な証拠にもなります。
記録は、あなた自身を守るための「盾」でもあるのです。
思考術⑥:完璧主義を捨てる勇気。「80点の介護」で自分を許そう
真面目で責任感の強い職員ほど、「常に100点の介護を提供しなければ」という完璧主義の罠に陥りがちです。
しかし、介護の現場に絶対的な「正解」は存在しません。
100点を目指し続けることは、やがて心身の燃え尽き(バーンアウト)に繋がってしまいます。

持続可能な介護のための「良い加減」
大切なのは、100点を目指すことよりも、安定して質の高い介護を「継続」することです。
そのためには、「今日はこれで十分」「80点の出来栄えだ」と、自分自身を認めて許してあげる勇気が必要です。
全てを完璧にこなそうとせず、時には「ここまでできればOK」という良い意味での「加減」を覚えましょう。
その少しの余裕が、利用者さんに対して穏やかな気持ちで接するための余白を生み出します。
完璧ではない自分を許すことが、結果としてより良いケアに繋がり、長くこの仕事を続けていくための秘訣なのです。
思考術⑦:仕事のストレスは職場に置いてくる!上手なオンオフの切り替え方
どんなに思考術を駆使しても、仕事で受けたストレスをゼロにすることは難しいでしょう。
だからこそ、そのストレスをプライベートな時間にまで持ち込まない「オンオフの切り替え」が極めて重要になります。

あなただけの「切り替えスイッチ」を見つける
仕事が終わったら、意識的に気持ちを切り替えるための「儀式」を持つのをおすすめします。
- 制服を脱ぐ時に、一日の嫌なことも一緒に脱ぎ捨てるイメージを持つ
- 職場の最寄り駅で電車に乗ったら、仕事のことは一切考えないと決める
- 帰宅途中に好きな音楽を大音量で聴く、少し遠回りして散歩する
- 家に帰ったら、熱いお風呂にゆっくり浸かる
何でも構いません。
あなただけの「切り替えスイッチ」を見つけ、仕事のストレスは職場という箱の中にきっちり置いてくる習慣をつけましょう。
この切り替えが上手になれば、プライベートな時間が充実し、それがまた翌日の仕事への活力となります。
心身の健康を維持し、バーンアウトを防ぐためにも、ぜひ意識してみてください。
まとめ:介護で利用者に怒られる経験を、明日への力に変えるために
今回は、介護の現場で利用者さんに怒られて落ち込んでしまう時の原因と、心を壊さないための具体的な思考術について解説しました。
最後に、この記事の要点を振り返ってみましょう。
- 利用者に怒られる原因は、認知症の症状やご本人の不安など、あなた以外の要因が大きい。
- 自分のせいだと抱え込まず、原因を客観的に分析することで心は軽くなる。
- 心を壊さないためには、以下の7つの思考術が有効。
- 「自分」と「役割」を切り離す
- 理不尽な言葉は「スルー機能」で受け流す
- 危険を感じたらまず「安全確保」
- 「優しくできない自分」を認めてあげる
- 「記録」を武器にチームで対応する
- 「80点の介護」で自分を許す
- オンオフの「切り替えスイッチ」を持つ
毎日心無い言葉を浴びせられれば、誰だって辛くなります。
「もう辞めたい」と感じるのも当然です。
しかし、あなたが感じているその辛さや理不尽さは、あなたを介護職としてより一層成長させてくれる貴重な経験でもあります。
今日お伝えした思考術を一つでも試してみて、まずはあなた自身の心を守ることを最優先してください。
それでもどうしても状況が改善せず、心が限界だと感じたら、それはあなたが悪いのではなく、その職場環境があなたに合っていないのかもしれません。
その時は、勇気を持って環境を変える、つまり転職という選択肢を考えることも、あなた自身のキャリアと人生を守るための立派な選択です。
また、大きな決断を下す前に、ご自身の心の状態を客観的に見つめ直すことも大切です。
厚生労働省が運営するポータルサイト「こころの耳」では、働く人のメンタルヘルス不調やストレスチェック、セルフケアに関する信頼性の高い情報が提供されています。
こうした公的な情報を参考に、ご自身の状況を整理してみるのも一つの方法です。
あなたのその優しさと、利用者さんを想う真摯な気持ちは、決して無駄にはなりません。
必ず、その力を必要としている場所や人がいます。
この記事が、あなたの心を少しでも軽くし、明日へ踏み出すための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。




コメント