「中堅なのに、なぜあの職員は仕事が遅いんだろう…」
「何度か注意はしたけれど、一向に改善しない…」
リーダーや管理者として、このような悩みを抱えていませんか?
経験年数を重ね、本来なら現場の主戦力となるべき介護職で仕事が遅い中堅職員がいると、チーム全体の業務効率に影響し、何より指導する側のあなたの精神的な負担は大きいものだと思います。

私自身も10年以上、様々な介護施設で多くの職員を見てきました。
仕事が早い新人、そして残念ながら仕事が遅いままの中堅職員も…。
現在は事務職員として現場を俯瞰する立場におり、その原因と背景がより客観的に見えるようになりました。
この記事では、単に「仕事が遅い中堅職員」を責めるのではなく、なぜそうなってしまうのかという原因を冷静に分析し、指導者であるあなたが明日から実践できる具体的な関わり方や改善策を、私の経験に基づいて徹底解説します。
この記事を読めば、あなたのその悩みは解決に向かい、職員本人とあなたの双方にとって、より良い職場環境を築くための具体的な一歩を踏み出せるはずです。
介護職で仕事が遅い中堅。考えられる5つの根本原因
まず大切なのは、感情的に「遅い!」と指摘する前に、なぜその中堅職員の仕事が遅くなってしまうのか、その根本的な原因を冷静に探ることです。
私が様々な施設を見てきた経験上、原因は本人のやる気だけの問題ではなく、複数の要因が複雑に絡み合っているケースがほとんどです。
ここでは、特に多く見られる5つの原因について、深掘りしていきます。

完璧主義で要領が悪い?優先順位がつけられない特徴
介護の仕事は、どこまでやっても「完璧」ということはありません。
しかし、責任感が強い職員ほど、一つの業務に対して完璧を求めすぎてしまう傾向があります。
質の高さを求めすぎて時間が足りなくなる
例えば、利用者さんの居室清掃で、隅々までピカピカにしないと気が済まなかったり、清拭タオルを何度も温め直したり。
一つひとつのケアは非常に丁寧で、それ自体は素晴らしいことです。
しかし、その結果、他の利用者さんを待たせてしまったり、次の業務に遅れが生じたりしては、チームとして問題です。
私が特養でリーダーをしていた頃も、非常に真面目で優しい中堅職員がいました。
彼は、利用者さん一人ひとりの記録を、まるで小説のように詳細に書かないと気が済まないのです。
その日の様子が手に取るように分かる素晴らしい記録でしたが、毎日そのために1時間以上残業していました。
これでは本人の負担が大きすぎますし、何より緊急時にサッと情報を確認したい他の職員にとっては、要点が掴みづらいというデメリットもありました。
「まあ、いっか」ができない真面目さ
介護現場では、限られた時間の中で多くの業務をこなすため、ある程度の「見切り」が必要です。
「この業務は8割の完成度で次に進もう」といった判断が、全体の業務を円滑に進める上で重要になります。
しかし、仕事が遅いと言われる中堅職員の中には、この「見切り」をつけるのが苦手な人がいます。
全ての業務を100点でこなそうとするあまり、結果として時間切れになってしまうのです。
これは、要領が悪いというよりは、真面目さや責任感の現れであることが多い点を、指導者として理解しておく必要があります。
マルチタスクが苦手で、いつも時間に追われてしまう
介護の現場は、まさにマルチタスクの連続です。
Aさんの排泄介助をしている最中に、Bさんのナースコールが鳴り、Cさんが立ち上がろうとしているのを見守る。
一つの業務に集中できる時間の方が珍しいくらいです。
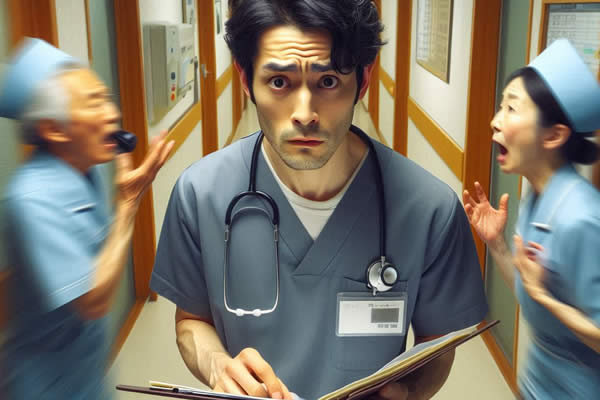
予測不能な割り込み業務への対応
多くの介護施設、特に特別養護老人ホームや有料老人ホームのような入所施設では、常に予測不能な事態が起こります。
一つの業務計画を立てていても、その通りに進むことは稀です。
仕事がスムーズに進む職員は、こうした割り込み業務に柔軟に対応し、頭の中で瞬時にタスクの優先順位を組み替えています。
しかし、マルチタスクが苦手な職員は、一つのことに集中すると周りが見えなくなりがちです。
ナースコールが鳴っても「今はこの介助中だから」と後回しにしてしまったり、割り込み業務に対応した後に「さて、次は何をするんだっけ?」と元の業務に戻れなくなってしまったりするのです。
思考が停止してしまう「パニック状態」
特に、複数の緊急事態が同時に発生すると、頭が真っ白になってフリーズしてしまうことがあります。
これは本人の能力というよりも、脳の情報処理の特性による部分が大きいです。
一つのことにじっくり取り組むのは得意でも、同時に複数のことを処理しようとすると、極端にパフォーマンスが落ちてしまうのです。
「あの人はいつも時間に追われてバタバタしている」ように見えるかもしれませんが、本人の頭の中は常にフル回転で、むしろ焦りからくる疲労でいっぱいになっている可能性があります。
「中堅だから」というプレッシャーと自信のなさから来る焦り
新人時代は「できなくて当たり前」と多めに見てもらえたことも、中堅になると許されなくなります。
「経験年数の割に仕事が遅い」と思われているのではないか、というプレッシャーは、本人が感じる以上に重くのしかかっています。

周囲の期待と現実のギャップ
中堅職員は、リーダーシップを発揮したり、後輩を指導したりといった役割を期待され始めます。
しかし、本人が自分の業務スピードに自信を持てていない場合、その期待が大きな負担になります。
「後輩に手本を見せなければいけないのに、自分自身が一番遅い…」
「リーダーに推薦されたけど、私なんかが務まるわけがない…」
こうした自己肯定感の低さが、さらなる焦りを生み、本来持っている力を発揮できなくさせるという悪循環に陥ってしまうのです。
指導者であるあなたが良かれと思って「もう中堅なんだから、しっかりしてよ」といった趣旨の発言をすると、それは激励ではなく、相手を追い詰める言葉になりかねません。
ミスを恐れるあまり、行動が遅くなる
プレッシャーを感じると、人はミスを極端に恐れるようになります。
「これで合っているだろうか」「間違えたらどうしよう」と一つひとつの行動に迷いが生じ、確認作業に過剰な時間を費やしてしまいます。
その結果、全体の業務スピードが著しく低下するのです。
自信を持ってスピーディーに業務をこなす介護職の仕事ができる人と比べ、常に不安を抱えながら仕事をしているため、精神的な消耗も激しくなります。
新人時代に適切な指導を受けられなかったスキルの偏り
今、中堅として働いている職員が新人だった頃の教育体制はどうだったでしょうか。
慢性的な人手不足の介護業界では、十分な新人研修が行われず、「見て覚えろ」というようなOJT任せの職場も少なくありません。

自己流の非効率なやり方が定着
もし、新人時代に非効率なやり方を教わったり、自己流で業務を覚えたりした場合、それが「当たり前」として定着してしまいます。
本人は真面目にそのやり方を続けているだけで、それが「遅い」原因であることに気づいていない可能性があります。
例えば、おむつ交換の際、物品の準備や動線に無駄が多く、一つひとつの作業に時間がかかっているかもしれません。
一度身についた癖を後から修正するのは、非常に根気がいる作業です。
指導する側も、「なぜこんな簡単なことができないんだ」と考えるのではなく、「もしかしたら、やり方そのものを知らないのかもしれない」という視点を持つことが重要です。
施設文化によるローカルルールの影響
私が複数の施設を経験して感じたのは、施設ごとに驚くほど多くの「ローカルルール」が存在するということです。
ある特養では当たり前だった記録の書き方が、別の有料老人ホームでは「非効率」とされたこともありました。
もしその中堅職員が、特定の施設文化に長く染まっていた場合、そのやり方が普遍的なものではないと認識できていない可能性があります。
「前の職場ではこうだった」という経験が、新しい環境への適応を妨げ、結果として業務の遅れにつながっているのかもしれません。
後輩指導や委員会の役割増で自分の業務に集中できない
中堅になると、純粋なプレイヤーとしての業務以外に、様々な役割が加わります。
本人も気づかないうちに、キャパシティオーバーに陥っているケースも少なくありません。

責任範囲の拡大と業務量の増加
- 後輩指導: 新人や実習生の指導係を任される。
- 委員会活動: 事故防止委員会やレクリエーション委員会などに所属し、資料作成や会議が増える。
- リーダー業務の補佐: シフト作成の手伝いや、リーダー不在時の代理を務める。
- 家族対応: より複雑なクレームや相談の初期対応を任される。
これらの業務は、目に見える形で時間を奪うだけでなく、「常に気に掛けておく」という精神的な負荷も伴います。
自分のケア業務に集中できる時間が減っているにもかかわらず、以前と同じ、あるいはそれ以上の成果を求められていては、仕事が時間内に終わらないのも当然と言えるかもしれません。
マネジメント能力の不足
プレイヤーとして優秀だった人が、必ずしもマネジメントが得意とは限りません。
後輩への指示の出し方や、自分の業務との時間配分の仕方が分からず、すべてを自分で抱え込んでパンクしてしまうのです。
これは本人の資質の問題だけでなく、中堅職員に対する適切なマネジメント研修を組織が提供してこなかった、という経営的な課題も潜んでいます。
指導者としては、その職員が現在どのような役割を担っていて、どれだけの業務量を抱えているのかを客観的に把握することが、問題解決の第一歩となります。
介護職で仕事が遅い中堅を改善へ導く。指導者の関わり方
原因を分析した上で、次はいよいよ具体的な関わり方です。
介護職で仕事が遅い中堅職員を、感情的に追い詰めるのではなく、着実に改善へと導くためには、指導者であるあなたの冷静で戦略的なアプローチが不可欠です。
一方的に「こうしろ」と指示するのではなく、本人と向き合い、一緒に考える姿勢が、信頼関係を築き、良い結果を生み出します。

「なぜ遅い?」はNG。本音を引き出す面談とヒアリングのコツ
多くの指導者がやってしまいがちなのが、「なんでそんなに仕事が遅いの?」と本人を問い詰めることです。
これは百害あって一利なし。
相手を萎縮させ、心を閉ざさせてしまうだけで、根本的な解決にはつながりません。
安全な場で1on1の時間を確保する
まず、他の職員がいない、静かで落ち着いた場所で、1対1で話す時間を作りましょう。
「最近、何か困っていることはない?」
「少し業務量が多いように見えるけど、大丈夫?」
このように、相手を気遣う言葉から入ることで、本音を話しやすい雰囲気を作ることができます。
私が事務職として職員面談を行う際も、決して「問題点を指摘する場」にはしません。
あくまで「あなたの現状を理解し、より働きやすくなるために会社として何ができるかを考える場」というスタンスを明確に伝えます。
詰問ではなく質問で、課題を具体化する
「遅い」という抽象的な言葉ではなく、具体的な業務に焦点を当てて質問を重ねていきましょう。
- 「一日の業務の中で、特に時間がかかると感じるのはどの部分かな?」
- 「〇〇さんの排泄介助の時、何かやりにくい点はある?」
- 「記録を書くのに、大体どれくらい時間がかかっている?」
このように具体的に聞くことで、本人も「自分は〇〇が苦手なんだ」と課題を客観的に認識できるようになります。
指導者は、答えを教えるのではなく、本人が答えを見つける手助けをするカウンセラーのような役割を意識すると良いでしょう。
業務の可視化と段取りの共有。一緒にタイムマネジメントを考える
本人が課題を認識できたら、次は具体的な改善策を一緒に考えていきます。
この時も、指導者が一方的にやり方を押し付けるのではなく、本人に考えさせ、実践させることが重要です。

タイムスケジュールの書き出しとボトルネックの特定
まず、一日の標準的な業務スケジュールを、時間軸に沿って書き出してもらいます。
「何時から何時まで、何をしたか」をできるだけ詳細に記録することで、どこに時間がかかっているのか、いわゆるボトルネックが可視化されます。
例えば、「午前中の入浴介助に想定以上の時間がかかり、午後のレクリエーション準備がいつもギリギリになる」といった課題が見えてくるかもしれません。
これに対して、「じゃあ、入浴介助の時間を5分短縮するには、どうしたらいいと思う?」と、具体的な改善アクションにつなげていきます。
優先順位付けのトレーニング
介護現場では、緊急度と重要度を天秤にかけ、瞬時に判断する能力が求められます。
この判断が苦手な職員には、一緒にトレーニングをしてみましょう。
例えば、想定される業務(ナースコール対応、定時の記録、レクリエーションの準備など)を付箋に書き出し、「緊急かつ重要」「重要だけど緊急ではない」といったマトリクスに分類していく練習をするのも効果的です。
私がリーダーだった頃、タイマーを渡し、「この記録は15分で」「この申し送り準備は10分で」と、ゲーム感覚で時間意識を持たせるトレーニングを取り入れたことがあります。
締め切り効果で集中力が高まり、ダラダラと作業する癖を改善するきっかけになりました。
小さな成功体験を積ませる。「介護職として優秀な人」へ育てる目標設定
自信を失っている職員に対して、いきなり高い目標を設定しても、プレッシャーになるだけです。
大切なのは、小さな成功体験を一つひとつ積み重ねさせ、自己肯定感を回復させてあげることです。

スモールステップでの目標設定
「明日から全部早くしろ」というのは無理な話です。
「まずは、午後の記録作成時間を5分短縮することから始めてみよう」
「今週は、申し送り前に必ず自分の担当ユニットを一周して、忘れ物がないか確認するのを目標にしよう」
このように、具体的で、少し頑張れば達成できるレベルの目標を設定します。
そして、達成できたら、必ずその場で具体的に褒めること。
「〇〇さん、今日記録早かったね!おかげで次の準備がスムーズに始められたよ、ありがとう」
この「承認」の言葉が、本人の次へのモチベーションになります。
「優秀な職員」の定義を共有する
そもそも、あなたの職場における「優秀な介護職員」とは、どのような職員でしょうか。
ケアの質が誰よりも高い人でしょうか?
誰よりも業務スピードが速い人でしょうか?
それとも、チームワークを大切にし、周りをよく見ている人でしょうか?
この定義が曖昧なままだと、職員は何を目指せばいいのか分かりません。
「私たちのチームが目指すのは、完璧なケアではなく、利用者さんが安全で快適に過ごせるケアを、時間内に安定して提供することだよ」と、チームとしての価値観を共有することも、指導者としての大切な役割です。
もしかしたら、その中堅職員は、スピードは遅くても、利用者さんの小さな変化に気づくのが得意かもしれません。
その強みを認め、伸ばしてあげることも、育成の一つです。
チームで支える体制づくり。バーンアウトを防ぐための環境改善
仕事が遅いという問題は、決してその職員一人の問題ではありません。
チーム全体の業務バランスや、サポート体制に問題が潜んでいることも多々あります。

個人攻撃にさせないチーム全体の課題として共有する
「〇〇さんが遅いから、みんなが迷惑している」という雰囲気を作ってしまうのは最悪です。
そうではなく、「チーム全体の業務効率を上げるために、何かできることはないか」という議題として、チームミーティングなどで話し合うことが重要です。
その中で、「〇〇さんの業務の一部を、手の空いている△△さんが手伝う」「情報共有の方法を見直し、申し送りの時間を短縮する」といった、チームで取り組める改善策が出てくるはずです。
動かない職員ややる気ない職員が他にいる場合、真面目な中堅職員にしわ寄せがいっている可能性も考えられます。
特定の個人を責めるのではなく、チーム全体のパフォーマンスという視点で問題を見つめ直しましょう。
バーンアウトの兆候を見逃さない
常に焦りやプレッシャーを感じながら仕事をしていると、心身ともに疲弊し、いわゆるバーンアウト(燃え尽き症候群)に陥る危険性があります。
- 遅刻や欠勤が増える
- 表情が乏しくなる
- 利用者さんへの関心が低下する
このような兆候が見られたら、危険信号です。
業務の改善指導と並行して、本人の心身の健康状態にも気を配り、必要であれば長期休暇の取得を促すなど、組織としてのケアが求められます。
指導しても改善しない…最終手段としての配置転換や転職の示唆
あらゆる手立てを尽くし、本人にも改善の意思が見られるにもかかわらず、どうしても状況が良くならない。
残念ながら、そうしたケースも存在します。
その場合は、本人の特性と現在の業務内容が、根本的にミスマッチである可能性を考えなければなりません。

本人の適性を見極めた配置転換の検討
例えば、突発的なマルチタスクが連続する特別養護老人ホームのフロア業務が苦手でも、一人ひとりとじっくり向き合える訪問介護や、比較的業務の流れが一定しているデイサービスの機能訓練担当などであれば、その能力を発揮できるかもしれません。
指導者として、また管理者として、本人の強みと弱みを客観的に評価し、施設内でより適した部署への配置転換を検討することも、重要なマネジメントです。
これは「罰」ではなく、本人がより輝ける場所を提供するという積極的な育成戦略と捉えるべきです。
本人のキャリアを考えた上での誠実な対応
それでもなお、施設内で適した場所が見つからない場合。
最終的な手段として、本人のキャリアを真剣に考えた上で、転職を視野に入れることを示唆するのも、指導者としての誠実な選択肢の一つだと私は考えます。
「今のうちの施設では、あなたの良さを最大限に活かせる場所を提供できなくて申し訳ない。でも、あなたのその真面目さや丁寧さは、別の環境なら必ず高く評価されると思う」
このように、本人の人格や能力を否定するのではなく、あくまで「環境とのミスマッチ」であることを伝え、次のステップを応援する姿勢を示すことが大切です。
もちろん、これは安易に口にすべき言葉ではありません。
指導者として、組織として、あらゆる努力を尽くした上での、最終手段であることを心に留めておいてください。
まとめ:介護職で仕事が遅い中堅職員への関わり方
今回は、仕事が遅い中堅介護職員に悩む管理者・指導者の方へ向けて、その原因と具体的な関わり方について、私の経験を交えながら解説しました。
重要なポイントを改めて整理します。
- 原因分析: まずは感情的にならず、「なぜ遅いのか」を冷静に分析する。完璧主義、マルチタスクの苦手、プレッシャー、過去の指導、業務量の増加など、原因は複合的である。
- 具体的関わり方:
- 「なぜ?」と詰問せず、1on1で本音を引き出す。
- 業務を可視化し、一緒にタイムマネジメントを考える。
- 小さな成功体験を積ませ、自己肯定感を育てる。
- 個人を責めず、チーム全体でサポートする体制を作る。
- 最終手段として、本人の適性を考えた配置転換やキャリアの相談に乗る。
大切なのは、一方的に「指導する」というスタンスではなく、「伴走する」という姿勢です。
あなたの関わり方一つで、自信を失っていた中堅職員は、チームにとってかけがえのない存在へと大きく変わる可能性を秘めています。
この記事が、明日からのあなたの指導のヒントとなり、あなたと職員、そして施設全体にとって、より良い未来を築くための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。




コメント