デイサービスでの仕事、本当に毎日お疲れ様です。
やりがいを感じる瞬間も多い一方で、「特定の利用者さんとの関わり方がどうしても難しい…」と感じていませんか。
心無い言葉に傷ついたり、理不尽な要求に疲れ果ててしまったり。
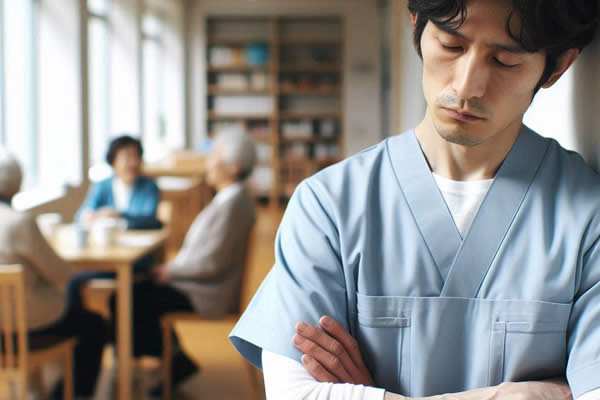
「もう限界、辞めたい」そう思ってしまうのは、決してあなただけではありませんし、あなたの心が弱いからでもありません。
この記事では、長年さまざまな介護現場を渡り歩いてきた私が、デイサービスで嫌な利用者と感じてしまうその背景と、あなたの心をすり減らさないための具体的な対処法を、私の経験を交えながら徹底的に解説します。
この記事を読み終える頃には、明日からの関わり方が少し楽になっているはずです。
【タイプ別】デイサービスの嫌な利用者と感じてしまう背景
なぜ、私たちは特定の利用者さんのことを「嫌だな」「苦手だな」と感じてしまうのでしょうか。
その感情を否定する必要は全くありません。
しかし、その行動の裏にある「背景」を少しだけ知ることで、私たちの心の負担は驚くほど軽くなることがあります。
ここでは、私がこれまで見てきた様々なケースを基に、タイプ別にその背景を探っていきましょう。

なぜ?デイサービスで暴言を吐く利用者の心理と隠れたサイン
「バカ」「役立たず」
面と向かって暴言を吐かれる経験は、どれだけキャリアを重ねても慣れるものではなく、深く心をえぐられますよね。
私が特別養護老人ホーム(特養)で働いていた頃、普段はとても物静かなAさんという女性がいました。
しかし、特定の若い男性職員に対してだけ、人が変わったように激しい言葉をぶつけるのです。
当初、私たちは「単なる相性の問題だろう」と片付けようとしていました。
しかし、観察を続けると、ある共通点が見えてきたのです。
それは、その職員がAさんの左側から急に声をかける時でした。
暴言の引き金は「不安」と「恐怖」
実はAさん、病気の後遺症で左側の視野が狭くなっており、認識しづらい方向から急に人が現れることに強い恐怖を感じていたのです。
彼女の暴言は、私たちに対する攻撃ではなく、自分自身を守るための必死の防衛反応でした。
このように、暴言の裏には、ご本人が抱える病気や障がいによる不安、痛み、認知機能の低下などが隠れているケースが少なくありません。
自分の思いをうまく言葉で伝えられないもどかしさが、攻撃的な言葉として現れてしまうのです。
見逃してはいけない「隠れたサイン」
利用者が暴言を吐く前には、何かしらのサインが出ていることが多いです。
- 表情がこわばる
- 貧乏ゆすりを始める
- 特定の話題や状況を避けるような素振りを見せる
- 声のトーンが低くなる
これらの小さな変化に気づき、「〇〇さん、何かお困りですか?」と一歩踏み込んで関わることで、感情の爆発を未然に防げる可能性があります。
暴言は、その人からの「助けて」というサインなのかもしれない。
そう視点を変えるだけで、私たちの受け止め方も少し変わってくるのではないでしょうか。
デイサービスの利用者が「わがまま」に見える行動の本当の理由
「レクリエーションに参加したくない」
「今日はお風呂に入りたくない」
集団生活の場であるデイサービスにおいて、こうした「拒否」の態度は、時に職員を悩ませ、「わがまま」だと感じさせてしまいます。
しかし、これもまた、ご本人の視点に立つと全く違う景色が見えてきます。
私がかつて勤務していた有料老人ホームは、企業の役員や経営者だった方が多く入居されていました。
彼らは、人生の大半を「自分で決断し、人に指示する」立場で過ごしてきた方々です。
そうした方々にとって、デイサービスでの「皆さん、今から〇〇をしますよ」という画一的なスケジュールは、自分のペースを乱される大きなストレスになり得ます。

「わがまま」ではなく「自己決定」の尊重
介護の基本は「自己決定の尊重」です。
頭では分かっていても、日々の業務に追われると、つい効率を優先してしまいがちです。
利用者の「やりたくない」という言葉は、わがままなのではなく、「自分で決めたい」という最後のプライドや、その人らしさの表れなのかもしれません。
もちろん、健康管理上どうしても入浴が必要な場合など、譲れないラインはあります。
しかし、その場合でも「なぜ入りたくないのか」という理由に耳を傾ける姿勢が重要です。
- 「肌が乾燥してカサカサするのが嫌だ」 → 保湿力の高い入浴剤を提案する
- 「みんなの前で裸になるのが恥ずかしい」 → タオルで体を隠しながら洗う、個浴を検討する
- 「昨日家で入ったから今日はいい」 → 「血行が良くなると足の痛みが和らぎますよ」とメリットを伝える
このように、拒否の理由を探り、代替案を提示することで、ご本人の納得感は大きく変わります。
「わがままな人」とレッテルを貼る前に、その言葉の裏にある「本当の気持ち」を探る。
それが、プロとしての関わり方だと私は考えています。
つい「むかつく」と感じてしまう…試すような言動への正しい理解
わざと水をこぼしたり、何度も同じ質問を繰り返したり。
こちらが困るのを楽しんでいるかのような、試すような言動。
正直、「むかつく」と感じてしまうのも無理はありません。

その感情は、あなたが介護職として真面目に向き合っている証拠です。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)で働いていた時のことです。
ある入居者さんが、私が訪室するたびに「〇〇がない」「△△が壊れた」と、まるで私を試すかのような訴えを繰り返していました。
最初は私も躍起になって対応していましたが、次第に疲弊していきました。
ある日、先輩職員に相談したところ、「あの人は、あなたに来てほしいだけだよ」と教えられました。
試す行動の根底にある「承認欲求」と「不安」
その方は、日中お部屋で一人で過ごす時間が長く、強い孤独感を抱えていました。
物をなくしたり、壊したりすることで、私という職員との接点を無理やり作り出し、自分の存在を確認しようとしていたのです。
いわゆる「かまってちゃん」と言われる行動も、根っこは同じです。
- 自分は忘れられていないだろうか?
- この人は、本当に自分のことを気にかけてくれているのだろうか?
こうした不安や承認欲求が、他者から見ると不可解で、時に腹立たしい行動として現れるのです。
もちろん、こうした行動に一つ一つ全力で応えていては、こちらの身が持ちません。
大切なのは、「この行動は、私個人への攻撃ではなく、その人の不安の表れなのだ」と客観的に理解することです。
そして、「訴え」そのものではなく、「孤独感」という根本的な課題にアプローチできないか、チームで考えることが重要になります。
デイサービスで起こりがちな利用者同士のトラブルと職員の関わり方
利用者さん同士のトラブルも、職員にとっては大きなストレス源です。
テレビのチャンネル争い、席の取り合い、悪口や陰口…。
まるで、学校の教室を見ているかのような光景が繰り広げられることもあります。
ここで職員が絶対にやってはいけないのは、どちらが正しいかを裁く「裁判官」になってしまうことです。

介入の基本は「中立」と「傾聴」
トラブルに介入する際は、まず以下の点を徹底する必要があります。
- 物理的に距離を離す: まずは興奮状態にあるお二人を別の場所に誘導し、クールダウンする時間を作ります。
- それぞれの言い分を別々に聞く: 必ず一人ずつ、周りに人がいない場所で話を聞きます。「そうだったのですね」「嫌な思いをされましたね」と、まずは相手の感情をすべて受け止める(傾聴)ことが重要です。
- 事実は何かを確認する: 感情的な部分と、実際に何が起こったのかという事実を切り分けて情報を整理します。
多くの場合、双方の言い分には食い違いがあります。
「〇〇さんが私の悪口を言った」
「そんなことは言っていない。挨拶を無視されたから文句を言っただけだ」
どちらが真実かを追求しても、水掛け論になるだけです。
大切なのは、「それぞれが、そう感じた」という事実を受け止めることです。
その上で、「お互いに気持ちよく過ごすためにはどうすればいいか」という未来志向の話に転換していくことが、職員の役割だと私は考えています。
私が事務職として現場を見ていると、若い職員ほど正義感が強く、白黒つけたがる傾向があります。
しかし、介護現場の人間関係は、単純な善悪で割り切れないことばかり。
曖昧さを受け入れることも、時には必要なスキルなのです。
危険も?デイサービスの利用者同士で物のやり取りが起きた際の対応
「これ、うちの畑で採れたからあげるわ」
「いつもお世話になってるから、これ使ってちょうだい」
利用者さん同士の、善意から始まる物のやり取り。
一見、心温まる光景に見えますが、実は様々なリスクが潜んでいます。
事務職員という立場から見ると、これは非常に注意が必要な問題です。

善意の裏に潜むリスク
- 食中毒・アレルギー: 手作りの漬物やお菓子などは、衛生管理が不明な上、他の利用者のアレルギーの原因になる可能性があります。
- 服薬管理への影響: 持病がある方に、良かれと思って渡した健康食品などが、普段飲んでいる薬の効果を妨げる危険性があります。
- 金銭トラブル: 「〇〇をあげたのにお返しがない」といった不満から、金銭の要求に発展するケースもゼロではありません。
- 不公平感: 特定の人だけが物をもらっている状況は、他の利用者の嫉妬や疎外感を生み、新たなトラブルの火種になります。
施設としての毅然とした対応が不可欠
こうしたリスクを防ぐため、多くの施設では「利用者同士での金品のやり取りは原則禁止」というルールを設けています。
もし、やり取りの現場を発見したり、報告を受けたりした場合は、感情的に注意するのではなく、施設のルールとして冷静に説明する必要があります。
- まずは善意に感謝を伝える: 「お気持ちは大変ありがたいのですが…」と、相手の善意を否定しない姿勢が大切です。
- ルールとその理由を説明する: 「皆さんの安全を守るため、施設では物のやり取りをご遠慮いただいています」と、毅然とした態度で伝えます。
- 家族にも情報共有する: ご家族にも施設のルールを理解してもらい、不要な物を持たせないなどの協力を依頼することも重要です。
「気持ちは嬉しいのですが、何かお礼をしたい場合は、ぜひ言葉で伝えてあげてください。それが一番嬉しいと思いますよ」
このように、代替案を示すことで、角を立てずに対応することができます。
職員個人の判断で曖昧にせず、組織として統一した対応をとることが、利用者と職員双方を守ることに繋がるのです。
デイサービスの嫌な利用者から自分の心を守るための具体的対処法
ここまで、嫌な利用者と感じてしまう行動の背景について解説してきました。
背景を理解するだけでも、少しは心が軽くなるかもしれません。
しかし、それでも日々のストレスがゼロになるわけではありません。
ここからは、より実践的に、私たち介護職が自分の心を守り、すり減らないようにするための具体的な対処法についてお話しします。
感情論ではなく、明日からすぐに使えるテクニックです。

【基本】苦手な利用者へのストレスを溜めない対応の三原則
私が長年の「渡り鳥」介護職人生でたどり着いた、苦手な利用者さんへの対応でストレスを溜めないための三つの原則があります。
それは「役割に徹する」「感情と事実を分ける」「完璧を目指さない」の3つです。
原則1:仕事上の「役割」に徹する
私たちは、利用者さんを「好き」になるために仕事をしているわけではありません。
私たちの仕事は、契約に基づき、必要な介護サービスを安全に提供することです。
「この人は嫌いだけど、介護のプロとして、やるべきことはきちんとやる」
この「役割意識」を持つだけで、相手の言動に個人的な感情を揺さぶられにくくなります。
私は訪問介護をしていた頃、どうしても相性の合わない利用者さんがいました。
そのお宅に向かう前は、いつも気分が重かったです。
しかし、玄関のドアを開ける前に一度立ち止まり、「私はこれから〇〇さんの介助をする介護職員だ」と心の中で宣言する儀式をしていました。
プライベートな自分と、仕事中の自分との間に一本線を引く。
この意識的な切り替えが、心をプロテクトしてくれます。
原則2:起きた「事実」と自分の「感情」を切り分ける
苦手な利用者さんに対応していると、「また何か言われるんじゃないか」と、ついネガティブな感情が先行してしまいます。
ここで重要なのが、「起きた事実」と、それによって引き起こされた自分の「感情」を意識的に切り分けるトレーニングです。
例えば、利用者から「あんたは気が利かないね」と言われたとします。
- 起きた事実: 利用者が「あんたは気が利かないね」と言った。
- 自分の感情: 「悲しい」「むかつく」「自分はダメな職員だ」
ここで注目すべきは、「事実」は一つでも、どう「感じる」かは自分次第だということです。
「悲しい」と感じる代わりに、「何かご不満な点がありましたか?具体的に教えていただけますか?」と、事実確認のコミュニケーションに切り替えることも可能です。
この切り分けは、介護記録を書く際にも非常に役立ちます。
感情的な言葉ではなく、「〇時〇分、〇〇の介助中に『気が利かない』との発言あり」と事実だけを記録する。
これを繰り返すことで、客観的に状況を捉える癖がつき、感情の波に飲み込まれにくくなります。
原則3:100点満点の「完璧なケア」を目指さない
真面目で責任感の強い職員ほど、「すべての利用者に満足してもらわなければならない」という思い込みに囚われがちです。
しかし、人間同士ですから、どうしても相性の良し悪しは存在します。
10人の利用者がいれば、2人からは好かれ、7人からは普通に思われ、1人からは好かれないかもしれない。
それで良いのです。
いや、それが普通なのです。
全員から100点を取ろうとするから苦しくなるのです。
「この利用者さんには、80点のケアを提供できれば十分」
「苦手なあの人には、まずは安全を守るという60点のケアを確実にこなそう」
このように、自分の中でハードルを調整し、「完璧じゃない自分」を許してあげることが、長くこの仕事を続ける上での秘訣だと私は思います。
嫌いな利用者を無視するのは絶対NG!プロとしての適切な距離感とは?
「もう関わりたくないから、いっそ無視してしまいたい」
精神的に追い詰められると、そう考えてしまう気持ちも分かります。
しかし、プロの介護職として「無視」という選択肢は絶対にあり得ません。
それは、単なる倫理観の問題だけではなく、法的なリスクも伴うからです。

「無視」が招く最悪の事態
職員による無視は、介護の専門用語で「ネグレクト(介護放棄)」と見なされる可能性があります。
これは、高齢者虐待防止法で定められた虐待行為の一つです。
- 安全配慮義務違反: 無視した結果、利用者が転倒したり、体調の急変に気づけなかったりした場合、施設や職員の責任が問われます。
- 尊厳の侵害: 無視は、一人の人間としての尊厳を深く傷つける行為です。
- 問題の悪化: 無視された利用者は、さらに強い言葉や行動で気を引こうとし、結果的に状況を悪化させるだけです。
「嫌い」という個人的な感情を、業務に持ち込んで利用者の安全や尊厳を脅かすことは、決して許されません。
「物理的距離」と「心理的距離」を使い分ける
では、どうすればいいのか。
答えは、「適切な距離感」を保つことです。
ここで言う距離には2種類あります。
- 物理的な距離:
必要以上に長く側にいる必要はありません。用件が済んだら「では、失礼します」と、速やかにその場を離れる。これも立派なスキルです。相手のパーソナルスペースに踏み込みすぎないことも意識しましょう。 - 心理的な距離:
これが最も重要です。相手の言葉を全て真に受けて、自分の心の中に入れないことです。まるで、自分との間に一枚、透明なバリアがあるようなイメージです。相手の言葉は、そのバリアに当たって地面に落ちていく。自分の中には入ってこない。
「好き」「嫌い」の二元論で考えると、どうしても感情的になってしまいます。
そうではなく、「業務上のパートナー」や「ケアの対象者」といった第三のカテゴリーを自分の中に作ると、冷静に対応しやすくなります。
これは冷たい態度をとることとは違います。
あくまで、自分の心を守るためのプロフェッショナルな技術なのです。
介護の現場で利用者にキレた…そうなる前に実践するアンガーマネジメント
もし、あなたが感情を抑えきれず、利用者さんに強い口調で何かを言ってしまった経験があるなら、自分を責めすぎないでください。
それだけ、あなたは真剣に仕事に向き合い、追い詰められていたということです。
しかし、同じことを繰り返さないためには、自分の「怒り」の感情と上手に付き合う方法を知っておく必要があります。
それがアンガーマネジメントです。

怒りは「二次感情」だと知る
まず知っておきたいのは、怒りは「二次感情」だということです。
どういうことかと言うと、怒りが湧き上がる前には、必ずその下に隠れた「一次感情」が存在するのです。
- 一次感情: 悲しい、辛い、不安、心配、がっかり、疲れた…
- 二次感情: 怒り(キレる)
例えば、利用者から暴言を吐かれてカッとなった時。
その怒りの下には、「自分の人格を否定されて悲しい」「一生懸命やっているのに分かってもらえなくて辛い」「また言われるかもしれないという不安」といった一次感情が隠れています。
この一次感情が、心の中のコップから溢れた時に、「怒り」となって爆発するのです。
つまり、キレないためには、一次感情の段階で自分の気持ちに気づき、セルフケアをすることが重要になります。
現場で使える!怒りのピークをやり過ごすテクニック
そうは言っても、カッとなってしまう瞬間は訪れます。
怒りの感情のピークは、長くて6秒と言われています。
この6秒をどうやり過ごすかが勝負です。
- 6秒ルール: 心の中で「1、2、3、4、5、6…」とゆっくり数える。
- その場を離れる: 「少し失礼します」と言って、トイレやスタッフルームなど、一人になれる場所に一旦避難する。
- 思考を停止する: 頭の中で「ストップ!」と叫び、それ以上ネガティブなことを考えないようにする。
- 違うことを考える: 全く関係のない、楽しいこと(今夜の晩ごはん、週末の予定など)を無理やり思い浮かべる。
これらのテクニックは、いわば応急処置です。
根本的な解決のためには、なぜ自分が「悲しい」「辛い」と感じたのかを後で振り返り、次のH3で解説する「相談」に繋げていくことが不可欠です。
一人で抱えないで!上司やチームに相談し組織で問題を解決する方法
「こんなことで相談したら、自分が未熟だと思われるんじゃないか」
「上司や先輩は忙しそうだから、話しかけにくい」
そう感じて、一人で悩みを抱え込んでしまう。
かつての私がそうでした。
しかし、事務職員として施設の運営側になった今、断言できます。
職員からの相談は、組織にとって非常に価値のある情報なのです。

なぜ組織は「相談」を求めているのか
あなたが「嫌な利用者」と感じるその問題は、決してあなた個人の問題ではありません。
- リスクマネジメント: 一人の職員が我慢している問題は、いつか必ず大きな事故やトラブルに繋がります。組織は、そうなる前に小さな芽を摘んでおきたいのです。
- ケアの質の向上: あなたが感じている課題は、他の職員も感じているかもしれません。情報を共有し、チームで対応策を考えることで、その利用者さんへのケアの質そのものが向上します。
- 労務管理: 職員が過度なストレスを抱え、心身の不調をきたして休職や退職に至ることは、組織にとって大きな損失です。職員が健やかに働ける環境を整えることは、組織の義務なのです。
だから、相談することは、決して「迷惑」でも「甘え」でもなく、組織の一員としての重要な「報告・連絡・相談」なのです。
上司を動かす「相談の仕方」
ただ、やみくもに「〇〇さんが嫌で、もう無理です!」と感情的に訴えるだけでは、上司もどう動いていいか分かりません。
相談する際は、少しだけ準備をしておくとスムーズです。
- 事実と感情を分けて伝える:
「(事実)〇月〇日、入浴介助の際に『早くしろ』と3回言われました。(感情)その言葉に焦ってしまい、精神的にとても辛かったです」 - 記録を提示する:
日々の介護記録に、言われたことや、それに対してどう対応したかを客観的に記録しておき、それを見せながら説明すると説得力が増します。 - 「どうしてほしいか」を具体的に伝える(Iメッセージ):
「(あなたは)なんとかしてください」ではなく、「(私は)一度、先輩に対応を代わってもらって、どのように関わっているか見学させていただけないでしょうか」
「(私は)次回のカンファレンスで、〇〇さんへの対応方法を議題として取り上げてほしいです」
と、「私」を主語にして具体的な要望を伝えると、上司も具体的なアクションを起こしやすくなります。
一人で100点の対応を目指す必要はありません。
チームで60点、70点の対応を安定して継続することのほうが、よほど価値があるのです。
「辞めたい」が限界のサイン。自分を守る退職や転職という選択肢
ここまで様々な対処法をお伝えしてきましたが、それでも心が限界に達してしまうこともあります。
「朝、職場に行こうとすると涙が出る」
「夜、眠れない日が続いている」
「仕事以外の時間も、ずっとあの利用者のことばかり考えてしまう」
もし、あなたがこんな状態にあるのなら、それはあなたの心が発している限界のサインです。
「辞めたい」と感じるのは、逃げではありません。自分自身を守るための、最も勇気ある決断の一つです。
とはいえ、一人で抱え込んでいると、正常な判断が難しくなってしまうこともあります。
もし誰にも相談できずにいるのなら、厚生労働省の働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」のような、公的な専門機関に頼ることも考えてみてください。
匿名で利用できる電話相談やSNS相談もあり、あなたの気持ちを専門家が受け止めてくれます。

自分を守ることが最優先
介護職は、人の役に立ちたいという優しい気持ちを持った人が多いです。
だからこそ、「自分が辞めたら、他の職員や利用者さんに迷惑がかかる」と、自分のことを後回しにしてしまいがちです。
しかし、あなたが心と体の健康を損なってしまっては、元も子もありません。
あなたが笑顔でいられなくなったら、良いケアなどできるはずがないのです。
まずは、自分を守ることを最優先に考えてください。
転職は「キャリアアップ」の機会でもある
私が様々な施設を渡り歩いた経験から言えるのは、職場環境が変われば、働きやすさは劇的に変わるということです。
- デイサービスの集団ケアやレクリエーションが苦手でも、訪問介護の一対一の関わりなら、じっくり利用者さんと向き合えるかもしれない。
- 利用者との密な関わりに疲れたなら、特別養護老人ホームのように、チームで役割分担しながら働くスタイルが合っているかもしれない。
- 夜勤のない働き方をしたいなら、日勤のみのクリニックや健診センターという選択肢もある。
「嫌な利用者」が原因で辞める、と考えるとネガティブに聞こえるかもしれません。
しかし、視点を変えれば、それは「自分に本当に合った職場環境は何か」を見つめ直し、新しいキャリアを築く絶好の機会なのです。
今の職場が、あなたのすべてではありません。
介護の世界は、あなたが思っている以上に広く、多様な働き方があります。
もし、今の場所がどうしても辛いなら、勇気を出して一歩踏み出すことを、私は心から応援します。
まとめ:デイサービスの嫌な利用者に悩むあなたへ、最後に伝えたいこと
最後までお読みいただき、本当にありがとうございます。
この記事では、デイサービスで嫌な利用者と感じてしまう行動の背景と、私たち介護職が自分の心を守るための具体的な対処法について、私の経験を交えながら解説してきました。
暴言やわがままに見える行動の裏には、ご本人が抱える病気や不安、そして「誰かに気づいてほしい」という声なきサインが隠れていることが少なくありません。
その背景を少し知るだけで、私たちの受け止め方は変わってきます。
しかし、理解しようと努めても、心が疲れてしまうのは当然のことです。
だからこそ、「プロの役割に徹する」「事実と感情を切り分ける」「完璧を目指さない」といった技術で、ご自身の心にバリアを張ってください。
そして、何よりも大切なのは一人で抱え込まないことです。
あなたの悩みは、決して個人の問題ではなく、チームで、組織で取り組むべき課題です。
勇気を出して上司や同僚に相談することは、あなた自身を守るだけでなく、結果的に施設全体のケアの質を高めることに繋がります。
もし、それでも心が限界で「辞めたい」と感じるのなら、それは決して逃げではありません。
あなた自身を守るための、最も正しい選択です。
あなたが笑顔で働ける場所は、必ず他にあります。
どうか、自分自身を責めないでください。
この記事が、明日からのあなたの心を少しでも軽くする一助となれば、これほど嬉しいことはありません。

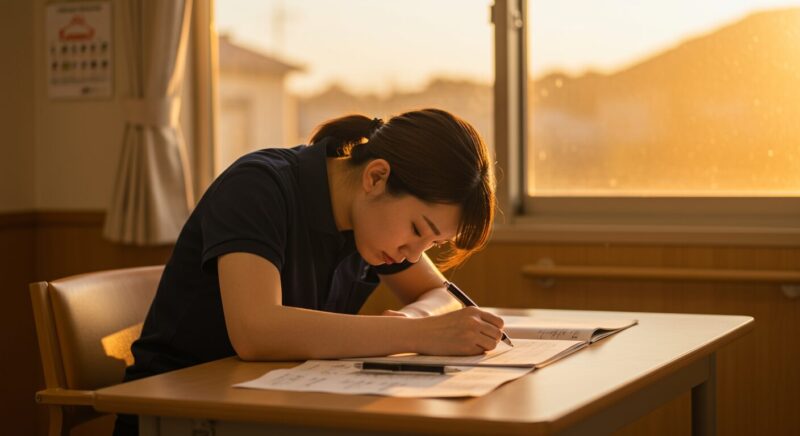


コメント