鳴り止まないコールランプ、フロアに響き渡る呼び出し音。
介護施設での頻回なナースコール対応、本当に心身ともに削られますよね。
「またか…」と、ついイライラしてしまう自分に気づき、そんな自分に嫌気がさしてしまう。
そんな悪循環に陥っていませんか。

この記事を読めば、そのイライラの根本的な原因が分かり、明日から現場で実践できる具体的な対策が見つかります。
もう一人で抱え込むのはやめにして、あなたの心を軽くするための第一歩を、ここから踏み出してみませんか。
介護施設のナースコールが頻回でイライラしてしまう根本原因
介護の現場で働く以上、ナースコールへの対応は私たちの重要な仕事の一つです。
しかし、そのコールがあまりにも頻回になると、冷静でいられなくなる瞬間があるのも事実です。
「どうしてこんなに呼ばれるんだろう」と感じるそのイライラの裏には、実はいくつかの明確な原因が隠されています。
このパートでは、まずその根本原因を一つひとつ丁寧に解き明かしていきます。
原因が分かれば、対策への道筋も見えてくるはずです。

なぜ?ナースコールを頻回に押す利用者の心理と理由
「何度も押さないでほしい」というのが私たちの本音かもしれません。
しかし、まずは利用者がなぜ頻繁にナースコールを押すのか、その心理や背景を理解することが、問題解決のスタートラインになります。
私がこれまで様々な施設で見てきた経験から、その理由は一つではなく、主に以下の4つのタイプに分けられると感じています。
不安や寂しさからくるコール
特に夜間や、居室で一人で過ごしている時間にコールが増える場合、その多くは精神的な不安や寂しさが原因です。
「誰かがそばにいてほしい」「一人でいるのが怖い」といった気持ちが、ナースコールを押すという行動に繋がっています。
この場合、用件を尋ねても「特に何もない」と答えられたり、職員の顔を見るだけで安心してコールが落ち着いたりすることも少なくありません。
これは、コールそのものが目的ではなく、誰かとの繋がりを確認するための手段になっているのです。
身体的な苦痛や不快感
もちろん、明確な身体的理由からコールが頻回になるケースも多くあります。
例えば、身体の痛み、痒み、トイレに行きたいという尿意・便意、あるいはベッドの上が暑い・寒いといった不快感などです。
特に、ご自身で身体を動かすことが難しい方や、うまく言葉で症状を伝えられない方の場合、その苦痛や不快感を知らせる唯一の手段がナースコールになります。
「またか」と思う前に、「何か身体的なサインではないか?」と一度立ち止まって考える視点が必要です。
認知症による見当識障害や記憶障害
認知症の症状が、ナースコールの頻回利用に直結することも珍しくありません。
例えば、今いる場所が分からなくなる「見当識障害」によって不安になりコールを押したり、数分前の出来事を忘れてしまう「記憶障害」によって、何度も同じ用件でコールしたりすることがあります。
これはご本人の意思とは関係なく、病気の症状として現れる行動です。
そのため、職員が「さっきも言いましたよ」と伝えても、ご本人にはその記憶がなく、状況の改善には繋がりにくいという難しさがあります。
職員への関心や確認行動
少し捉え方が難しいかもしれませんが、職員の気を引きたい、試したいという気持ちからコールを押す方もいらっしゃいます。
これは、職員とのコミュニケーションを求めている場合や、自分の存在を認めてほしいという承認欲求の表れであることも考えられます。
あるいは、過去の経験から「強く言わないと動いてくれない」という学習をしてしまい、要求を通すための手段としてコールを連打するというケースも見受けられます。
イライラの正体は「業務の停滞」と「認められない徒労感」
では、なぜ私たちは利用者のそうした心理を頭では理解していても、イライラしてしまうのでしょうか。
それは、私たちの感情が「優しさ」や「思いやり」だけでできているわけではないからです。
現場で働く職員側の視点から、イライラの正体を分析してみましょう。
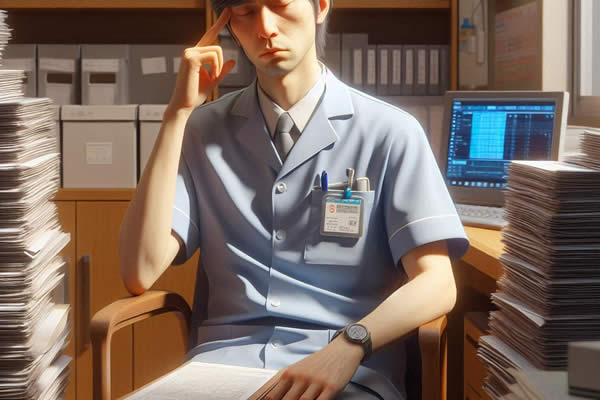
一つのコールに対応している間に、他の利用者のケアが中断されたり、計画していた業務がどんどん後ろ倒しになったりする。
この「業務の停滞」に対する焦りが、イライラの大きな原因の一つです。
特に、時間内に終わらせなければならない業務が山積している中でコールが鳴り響くと、「今じゃないのに!」という気持ちが湧き上がるのは自然なことです。
さらに深刻なのが、「認められない徒労感」です。
一生懸命に対応しても、数分後にはまた同じコールが鳴る。
感謝されるどころか、さらに要求がエスカレートすることさえあります。
まるで、ゴールの見えないマラソンを走らされているような、出口のないトンネルを彷徨っているような感覚。
「自分の頑張りは、一体何なのだろう」という虚しさが、やがて怒りや無気力へと変わっていくのです。
現在、私が事務職として現場を俯瞰する立場になって改めて感じるのは、この徒労感が職員のモチベーションを最も蝕む要因だということです。
「ナースコールを無視したい」と思ってしまう自分への罪悪感
コール対応に追われ、心身ともに限界を感じたとき、「少しだけ無視してしまったら…」という考えが頭をよぎった経験はありませんか。
そして、そう考えてしまった自分に対して、「なんてひどい介護職員なんだろう」と強い罪悪感を抱いてしまう。
これは、多くの真面目な介護職員が経験する苦しい葛藤です。

私たちは専門職として、利用者の安全と尊厳を守るという倫理的な責任を負っています。
ナースコールの放置が、最悪の場合、虐待や重大な事故に繋がりかねないことも理解しています。
だからこそ、コールを無視したいという感情と、専門職としての倫理観との間で板挟みになり、一人で苦しんでしまうのです。
しかし、覚えておいてほしいのは、そうした感情が芽生えるのは、決してあなたが冷たい人間だからではないということです。
それは、あなたの心が助けを求めているサインであり、今の働き方が限界に達しているという警告なのです。
特に認知症の方のナースコール連打に対応する難しさ
数あるコール対応の中でも、特に精神的な負担が大きいのが、認知症の利用者による「ナースコールの連打」です。
先ほども触れましたが、認知症の症状として、コールを押したこと自体を忘れてしまい、何度も繰り返し押してしまうことがあります。

居室に到着すると「何も押してないよ」と言われたり、用件を済ませてナースコールを手の届かない場所に置いたはずが、数分後にはまたどこからか見つけ出して鳴らしていたり。
特養で働いていた頃、一晩中特定の利用者さんのコール対応に追われ、他の利用者のケアがほとんど手につかなかった経験は一度や二度ではありません。
こうした状況は、まさに「先の見えない戦い」です。
対応しても感謝されず、状況も改善しない。
この繰り返しが、職員の心を少しずつすり減らし、「もうどうすればいいんだ」という無力感に繋がっていくのです。
夜勤など一人体制でナースコールが鳴りっぱなしになる状況
日中であれば、他の職員と協力したり、応援を頼んだりすることも可能です。
しかし、職員の数が少なくなる夜勤、特に一人体制でフロアを見ているときの頻回なナースコールは、まさに悪夢と言えるでしょう。
あちこちで同時にコールが鳴り、どれから対応すればいいのかパニックになる。
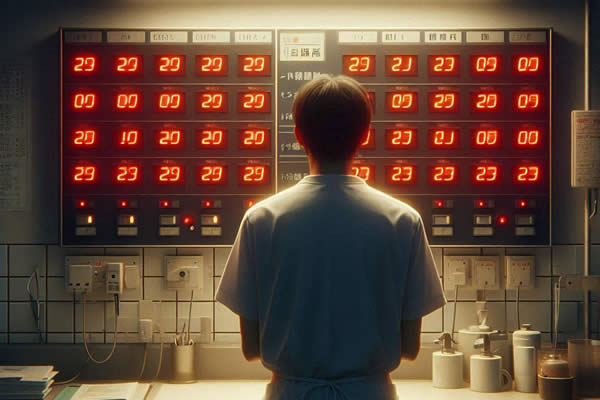
一つの対応に時間がかかっていると、他のコールが鳴りっぱなしになり、「何かあったのではないか」という不安と焦りに襲われる。
相談できる相手もおらず、たった一人でフロア中の安全と安心を守らなければならないというプレッシャーは計り知れません。
休憩や仮眠もままならず、肉体的にも精神的にも追い詰められていく。
このような過酷な状況下で、ナースコールに対してイライラするな、冷静でいろ、と言う方が無理な話です。
この状況は、個人の資質の問題ではなく、明らかに労働環境と体制の問題なのです。
介護施設のナースコールが頻回でイライラしないための具体的対策
ここまで、頻回なナースコールでイライラしてしまう原因を深掘りしてきました。
原因が分かれば、次に見えてくるのは具体的な「対策」です。
精神論だけで「利用者の気持ちを考えましょう」「優しく接しましょう」と言うつもりはありません。
そんなことは、皆さん十分すぎるほど分かっているはずだからです。
ここでは、私が様々な施設を渡り歩く中で実践してきた、また、事務職という立場から見て効果的だと感じる、明日から現場で使える具体的な対策を厳選してご紹介します。
個人で始められることから、チームで取り組むべきことまで、段階的に解説していきます。

【対策①】まずは記録から。客観的な事実で状況を把握・共有する
感情的に「〇〇さんのコールが多くて大変だ」と訴えても、なかなか建設的な話し合いには繋がりません。
そこで、まず最初に取り組むべき最も重要な対策が「記録」です。
面倒に感じるかもしれませんが、これが全ての改善の土台となります。
いつ、どんな内容でコールが鳴ったか
専用のシートを用意するか、日々の申し送りノートの片隅でも構いません。
以下の項目を、できるだけ客観的に記録してみてください。
- 日時: 何月何日の何時何分か
- コールの内容: 「トイレに行きたい」「お茶が飲みたい」「寂しい」など、利用者の訴え
- 対応内容: 実際に職員が行ったケア
- 対応後の様子: コールが落ち着いたか、またすぐに鳴ったかなど
これを数日間続けるだけでも、特定の時間帯にコールが集中している、特定の訴えが多い、といった傾向が見えてきます。
記録をチームで共有する意味
記録は、個人のためだけのものではありません。
これをチームで共有することで、初めて意味を持ちます。
カンファレンスやミーティングの場で、「この記録を見ると、〇〇さんは夕食後に不安が強くなる傾向があるようです」「トイレの訴えが多いので、排泄パターンを見直しませんか?」といった、客観的なデータに基づいた具体的な議論が可能になります。
これにより、「一人の職員が大変」という属人的な問題から、「チームで取り組むべき課題」へと昇華させることができるのです。
【対策②】認知症ケアの工夫で「押さなくても安心」な環境を作る
特に認知症が原因でコールが頻回になっている場合、ただ対応するだけでは状況は改善しません。
発想を転換し、「利用者がナースコールを押さなくても安心して過ごせる環境」をいかに作るか、という視点が重要になります。

不安を和らげる声かけ
不安からコールを押している利用者に対しては、「何かあったら押してくださいね」という声かけだけでは不十分な場合があります。
むしろ、「1時間後にまた様子を見に来ますね」「〇時になったらお茶を入れに来ます」といった、具体的な時間を約束する方が効果的です。
これにより、利用者の中に「待っていれば職員が来てくれる」という見通しが立ち、漠然とした不安が軽減されます。
もちろん、約束は必ず守ることが大前提です。
環境調整
利用者を取り巻く物理的な環境を整えることも、非常に有効なアプローチです。
例えば、有料老人ホームで働いていた頃、トイレの場所が分からず不安になっていた方のために、ベッドからトイレまでの動線に分かりやすい色のテープを貼ったり、夜間でも見えるように小さな明かりを設置したりしたところ、トイレ関連のコールが劇的に減少した経験があります。
他にも、家族の写真や使い慣れた物をベッドサイドに置く、カレンダーや時計を見やすい位置に設置するなど、その人が安心できる環境を整える工夫はたくさんあります。
先回りして対応する
先ほどの記録がここでも活きてきます。
記録から利用者の生活リズムやコールのパターンを分析し、訴えがありそうな時間帯の少し前に、こちらから訪室して声をかけるのです。
「そろそろトイレはいかがですか?」「お背中がかゆくなっていませんか?」と先回りしてケアを行うことで、利用者がコールを押す必要そのものをなくしていくことができます。
これは「御用聞き」になることとは違います。
専門職としての観察眼とアセスメントに基づいた、プロアクティブ(積極的)な関わり方です。
【対策③】「またですか?」と言わない。信頼関係を築く対応のコツ
分かってはいても、つい口から出てしまいがちな「またですか?」「さっきも言いましたよね」といった言葉。
これらの言葉は、百害あって一利なしです。
利用者の自尊心を傷つけ、職員への不信感を募らせるだけで、何一つ良い結果を生みません。
ここでは、利用者との無用な対立を避け、信頼関係を築くためのコミュニケーションのコツをお伝えします。

第一声の重要性
コール対応で居室に入るときの第一声は、極めて重要です。
たとえ内心イライラしていても、まずは「〇〇さん、どうされましたか?」と穏やかな口調で尋ねることを徹底してみてください。
否定的な言葉から入らないだけで、その後の会話の流れが大きく変わります。
忙しいときは難しいかもしれませんが、少しだけ腰をかがめて目線を合わせる、手を握るなどの非言語的なコミュニケーションも、相手に安心感を与える上で非常に効果的です。
傾聴の姿勢
利用者の訴えが、たとえ理不尽に感じられたり、事実と異なっていたりしても、まずは一度、最後まで話を遮らずに聴く「傾聴」の姿勢が大切です。
相手は、ただ自分の言い分を聴いてほしいだけなのかもしれません。
「そうなんですね」「〇〇ということがあったのですね」と、まずは相手の言葉を一度受け止める(受容)。
その上で、「でも、〇〇は今すぐには難しいので、代わりに△△はいかがですか?」と代替案を提示する(Iメッセージ)。
このプロセスを経ることで、利用者の興奮が収まり、冷静に話ができるケースは少なくありません。
【対策④】ノイローゼになる前に。自分の感情を守るアンガーマネジメント
どんなに対策を講じても、コール対応でイライラしてしまう瞬間をゼロにすることは難しいでしょう。
大切なのは、その怒りの感情に飲み込まれず、うまく付き合っていく術を身につけることです。
これは、利用者さんを守るためだけでなく、介護職として長く働き続けるために、あなた自身の心を守るための重要なスキルです。

6秒ルール
怒りの感情のピークは、長くて6秒と言われています。
カッとなったら、すぐに反応するのではなく、心の中で「1、2、3、4、5、6…」とゆっくり数えてみてください。
あるいは、一旦その場を静かに離れ、深呼吸をするのも良いでしょう。
このわずかな時間で、衝動的な言動をぐっとこらえることができます。
私も現場時代、どうしても我慢できないときは、スタッフルームのトイレに駆け込み、数秒間だけ気持ちをリセットするということをよくやっていました。
コーピングレパートリーを持つ
ストレスを感じたときに、その気持ちを和らげるための自分なりの方法(コーピングレパートリー)を、あらかじめいくつか用意しておくことも有効です。
「好きな音楽を聴く」「甘いものを食べる」「同僚と愚痴を言い合う」「仕事帰りに買い物をする」など、何でも構いません。
ポイントは、「これをすれば少し気分が晴れる」という選択肢を複数持っておくことです。
そうすることで、ストレスに対する心の耐性が高まります。
完璧主義をやめる
介護職員は真面目で責任感の強い人が多いからこそ、「全てのコールに完璧に対応しなければならない」という思い込みに囚われがちです。
しかし、限られた時間と人員の中で、それは不可能です。
時には「まあ、いいか」「今はこれが限界だ」と、良い意味で諦めることも必要です。
100点満点のケアを目指すのではなく、60点でも70点でも、今の状況でできるベストを尽くせば十分。
そのように考えるだけでも、心の負担はかなり軽くなるはずです。
もし、こうした怒りの感情との付き合い方について、より専門的な知識やテクニックを学びたいと感じたら、専門機関の情報を参考にしてみるのも良いでしょう。
より詳しい情報は、一般社団法人日本アンガーマネジメント協会の公式サイトで確認することができます。
【対策⑤】チームで解決へ。ICT機器の活用と業務改善の視点
ここまでは主に個人でできる対策を中心にお伝えしてきましたが、頻回なナースコールの問題は、最終的には施設全体、チームで取り組むべき課題です。
個人の努力には限界があり、仕組みとして改善しなければ、根本的な解決には至りません。

インカムの活用による情報共有と応援要請
インカム(無線機)を導入している施設も多いと思いますが、それを最大限に活用することが重要です。
例えば、一人の利用者のコール対応に時間がかかりそうなとき、「〇号室の対応に入ります。長引きそうなので、他のフロアフォローお願いします」とインカムで全体に発信する。
これにより、他の職員が状況を把握し、応援に入ったり、他のコールをカバーしたりといった連携がスムーズになります。
「助けて」と言える文化をチーム内に作ることが、職員の精神的な孤立を防ぎます。
見守りセンサーや介護ロボット導入の可能性
近年、ICT技術の進化は目覚ましく、介護現場でも様々な機器が導入され始めています。
例えば、利用者の離床や心拍数の変化を検知して知らせる「見守りセンサー」があれば、利用者がコールを押す前に、あるいは押せない状況でも異常を察知できます。
私が今いる施設でも一部導入していますが、これにより夜間の巡視業務の負担が軽減され、本当にケアが必要な人に時間を割けるようになったという声が上がっています。
もちろん導入にはコストがかかりますが、長期的に見れば、職員の離職防止やケアの質の向上に繋がり、経営的なメリットも大きいと私は考えています。
施設全体でコール対応の優先順位付けルールを作る
複数のコールが同時に鳴ったとき、どの利用者から対応すべきか。
この判断を個々の職員に委ねていると、迷いや混乱が生じ、対応の遅れに繋がります。
そこで、「転倒リスクが高い方を最優先する」「緊急性の低い『お茶が飲みたい』などのコールは、他のケアが一段落してから対応する」といった、施設としての明確なルール(トリアージ)を設けることが有効です。
もちろん、このルールは利用者や家族にも丁寧に説明し、理解を得ておく必要があります。
これにより、職員は迷いなく動けるようになり、「なぜ自分は後回しにされるのか」といった利用者からの不満を減らすことにも繋がります。
まとめ:介護施設の頻回なナースコールでイライラしないために
今回は、介護施設の頻回なナースコールにイライラしてしまう原因と、その具体的な対策について、私の経験を交えながら詳しく解説してきました。
最後に、この記事の要点を振り返ります。
頻回なナースコールにイライラしてしまうのは、あなたの心が狭いからではありません。
その背景には、利用者の不安や身体的苦痛、認知症の症状といった様々な理由があり、職員側にも業務の停滞や認められない徒労感といった明確な原因が存在します。
そして、この問題は決して精神論で解決できるものではなく、具体的な対策を講じることが可能です。
- 記録をとって客観的に状況を把握する
- 利用者が安心できる環境を整え、先回りしてケアする
- 信頼関係を築くコミュニケーションを心がける
- 自分の感情を守るアンガーマネジメントを身につける
- チームや組織として仕組みで解決する
これらの対策を、全て一度にやろうとする必要はありません。
まずは明日、あなたが「これならできそう」と感じた一つのことから試してみてはいかがでしょうか。
例えば、一人の利用者のコール記録をつけてみる。
あるいは、コール対応のときに、いつもより少しだけ穏やかな第一声を心がけてみる。
そんな小さな一歩が、あなたの心を少し軽くし、ひいては職場全体の空気を変えるきっかけになるかもしれません。
あなたは、一人ではありません。
同じように悩み、葛藤している仲間は、全国にたくさんいます。
この記事が、鳴り止まないコールの中で奮闘するあなたの、ささやかなお守りとなれば幸いです。




コメント