介護の現場で、特定の利用者さんからの絶え間ない呼び出しに、心がすり減っていませんか?
「いっそ無視できたら楽なのに…」
真面目なあなたほど、そう思ってしまう自分を責めているかもしれません。
その気持ち、痛いほどよく分かります。

しかし、単に要求を退けるだけでは、問題は解決しません。
この記事では、老人のかまってちゃんを、なぜ無視したくなってしまうのか、その根本にある心理を紐解き、あなたの心を壊さずに済むプロの対処法を、私の10年以上の現場経験を基に具体的にお伝えします。
この記事を読めば、明日からあなたの対応は確実に変わるはずです。
なぜ?「老人のかまってちゃん」を無視したくなる心理と原因
介護の現場で働いていると、特定の利用者さんからの頻繁な要求に、「またか…」とうんざりしてしまう瞬間は、誰にでもあるのではないでしょうか。
「無視したい」という感情は、あなたが冷たい人間だからではありません。
むしろ、真面目に向き合おうとすればするほど、心身ともに疲弊し、防衛本能として自然に湧き上がってくる感情なのです。
私が特別養護老人ホームで働いていた頃も、ひっきりなしにナースコールを押し、「テレビをつけて」「ティッシュを取って」「寂しい」と訴え続ける方がいました。
その方の対応に追われるあまり、他の利用者さんのケアが後回しになり、焦りと罪悪感でいっぱいになった経験は一度や二度ではありません。
しかし、なぜその方は、そこまでして私たちの気を引こうとするのでしょうか。
その行動の裏にある心理や原因を理解することで、「無視したい」というあなたの感情も、少しずつ変化していくかもしれません。
ここでは、つい無視したくなってしまう「かまってちゃん」と呼ばれる高齢者の行動について、その背景を深掘りしていきます。

孤独や不安の裏返し?「かまってちゃん」になってしまう高齢者の心理
人が誰かに「構ってほしい」と感じるのは、ごく自然な感情です。
特に高齢期には、それまでの人生で経験しなかったような、様々な「喪失」が訪れます。
例えば、長年勤めた会社を退職して「社会的役割」を失ったり、配偶者や友人と死別して「大切な人」を失ったり。
あるいは、身体機能が衰えて「健康」を失い、今まで当たり前にできていたことができなくなる、といった経験です。
これらの喪失は、ご本人が思う以上に大きな孤独感や、「この先どうなってしまうのだろう」という漠然とした不安につながります。
有料老人ホームに勤務していた時のことです。
ある入居者様は、元々は大きな会社の社長で、常に多くの部下に囲まれ、人に指示を出すのが当たり前の生活を送っていました。
しかし、引退して施設に入居されてからは、その役割を失った寂しさからか、職員に対して非常に細かい要求を繰り返すようになりました。
「カーテンの閉め方が悪い」「お茶の温度が違う」といった些細なことです。
最初は私たち職員も「また始まった…」と辟易していましたが、ある時、その方の行動が、実は「誰かと繋がっていたい」「自分の存在を認めてほしい」という、強い孤独感の裏返しなのではないかと気づきました。
誰かに指示を出し、それに相手が応えてくれるというやり取りを通して、かろうじてご自身の存在価値を確認しようとされていたのです。
このように、過度に見える要求の背景には、本人の寂しさや不安といった、切実な心理が隠れているケースが少なくありません。
それは認知症のサインかも?性格の問題と見分けるポイント
「あの人はもともと、わがままな性格だから」
そう片付けてしまう前に、少し立ち止まって考えてみてほしいことがあります。
その「かまってちゃん」な言動が、実は認知症の初期症状や、それに伴う周辺症状(BPSD)のサインである可能性です。
もちろん、元々の性格が影響している場合もあります。
しかし、以前と比べて明らかに言動が変わった場合は、注意深く観察する必要があります。

見当識障害による不安
認知症の中核症状の一つに、見当識障害があります。
これは、時間や場所、人が分からなくなる症状です。
「今がいつなのか」「ここがどこなのか」が分からなくなることは、計り知れない不安を生みます。
その不安を解消したくて、何度も職員に「今日は何日?」「私はどこにいるの?」と確認しに来るのです。
これは、あなたを困らせたいのではなく、ご本人が混乱と不安の中にいるSOSサインなのです。
実行機能障害による混乱
物事を順序立てて考え、計画的に実行することが難しくなるのが実行機能障害です。
例えば、「服を着替える」という単純な動作にも、「まず肌着を着て、次にシャツを着て…」という段取りがあります。
この段取りが分からなくなってしまうため、「どうすればいいか分からない」と助けを求めてくるのです。
「そんなことくらい自分でできるでしょう」と思ってしまうような些細な要求も、ご本人にとっては切実な問題なのです。
不安・焦燥感
認知症の周辺症状として、理由のない強い不安や焦燥感にかられることがあります。
夕方になると「家に帰らなくては」と落ち着かなくなる「帰宅願望」もその一つです。
このような時、ご本人は強い不安の中にいるため、誰かにそばにいてほしくて、何度も呼びかけたり、後をついてきたりすることがあります。
これらの症状を単なる性格の問題と見分けるには、「以前のその人と比べてどう変わったか」という視点が非常に重要です。
- 以前は穏やかだったのに、急に何度も同じことを聞くようになった
- 日付や曜日を頻繁に間違えるようになった
- 今までできていた身の回りのことが、うまくできなくなった
もしこのような変化が見られたら、それは性格ではなく、病気が原因かもしれません。
特養にいた頃、物静かで穏やかだった方が、ある時期から急に他の入居者さんの部屋に入り込んだり、大声を出したりするようになりました。
当初は職員も対応に困惑しましたが、結果的にそれは認知症の進行による症状だと分かりました。
私たちは、その方の「行動」だけを見るのではなく、「なぜその行動に至ったのか」という背景を探る必要があるのです。
この記事では、あくまで現場で気づくための基本的なポイントに絞って解説しました。
もし、認知症の症状や公的な支援制度について、より専門的で正確な情報を確認したい場合は、厚生労働省が提供している公式サイトも参考にしてみてください。
「老人のかまってちゃん病」と言われるほどの、嫌われる老人の特徴とは?
一方で、認知症などの病的な要因とは別に、その方の言動によって周囲から敬遠されてしまうケースも、残念ながら存在します。
現場の職員たちの間で、半ば冗談のように「かまってちゃん病」と揶揄されてしまう方には、いくつかの共通した特徴が見られます。
あなたの周りにいる、思わず「いるいる…」と頷いてしまうような方を思い浮かべてみてください。

自分の話ばかりで、人の話は聞かない
会話のキャッチボールができず、常に自分の話したいことだけを一方的に話し続けるタイプです。
こちらの都合はお構いなしに、延々と過去の自慢話や苦労話、あるいは他人の噂話を繰り返します。
相槌を打つと「聞いてくれている」と勘違いし、さらに話が長くなるという悪循環に陥りがちです。
他の利用者や職員への嫉妬や悪口が多い
自分に注目が集まっていないと気が済まず、他の利用者さんが職員と楽しそうに話していると、わざと割り込んできたり、後でその利用者さんや職員の悪口を言ったりします。
他人を貶めることで、相対的に自分の価値を上げよう、あるいは自分のほうを向かせようとする、少し屈折した承認欲求の表れと言えるかもしれません。
感謝の言葉がなく、要求ばかりがエスカレートする
どんなに親切に対応しても、「ありがとう」の一言もなく、それが当たり前だと思っているタイプです。
むしろ、一つの要求に応えると、「あれもやって」「これもやって」と、要求がどんどんエスカレートしていきます。
こちらが親切心から行ったことでも、彼らにとっては「やってもらって当然の権利」と認識されてしまうのです。
このような特徴を持つ方への対応は、本当に骨が折れます。
しかし、こうした言動の根底にも、やはり「誰かに認められたい」「自分は価値のある人間だと思いたい」という、強い承認欲求や孤独感が隠れていることを、心の片隅に留めておくと、少しだけ冷静になれるかもしれません。
なぜか自分だけ?年寄りから話しかけられやすい人の共通点
「どうして、いつも私ばっかり捕まるんだろう…」
フロアに他の職員もいるのに、なぜか特定の利用者さんが自分にだけ集中的に話しかけてきたり、要求してきたりする。
そんな経験はありませんか?
実は、高齢者から特に話しかけられやすい職員には、いくつかの共通点があります。
そして、それは皮肉なことに、介護職としてのあなたの「長所」でもあるのです。

優しくて断れないオーラが出ている
困っている人を見ると放っておけない、優しい性格の持ち主です。
相手の要求を無下に断ることができず、「いいですよ」「やりましょうか?」とつい引き受けてしまいます。
利用者さんは、誰が自分の要求を一番聞いてくれるかを実によく観察しています。
あなたの優しさは、彼らにとって「この人は頼みやすい人だ」という格好の目印になってしまっているのです。
聞き上手で、つい長く話を聞いてしまう
相手の話に真剣に耳を傾け、上手に相槌を打ち、共感を示すことができる人です。
あなたのその姿勢は、利用者さんにとって非常に心地よく、「この人にもっと話を聞いてほしい」と思わせます。
私も若い頃は、利用者さんの話を遮らずに最後まで聞くことが、良い介護だと信じていました。
しかしその結果、一人の利用者さんに30分以上も捕まってしまい、他の業務が全く進まず、先輩から叱責されるという失敗を何度も繰り返しました。
反応が良く、相手を喜ばせてしまう
相手の話に「すごいですね!」「そうだったんですか!」と、少しオーバー気味に反応してしまう人です。
あなたの良い反応は、話している相手を喜ばせ、承認欲求を満たします。
その結果、相手は「この人と話していると楽しい」と感じ、ますますあなたに話しかけてくるようになるのです。
これらの特徴は、本来であれば素晴らしいコミュニケーション能力であり、あなたの美点です。
しかし、介護という時間も人員も限られた現場においては、時として自分自身を追い詰める原因にもなりかねない、ということを知っておく必要があります。
病気アピールが激しい、依存心の強い高齢者への初期対応
「胸が苦しい」「頭が痛い」「めまいがする」
利用者さんからの身体的な不調の訴えは、介護職にとって最も対応に気を使うものの一つです。
本当に緊急性のある症状かもしれませんし、あるいは気を引きたいだけの「病気アピール」かもしれません。
ここで重要なのは、決して自己判断で「またいつものやつだ」と決めつけないことです。

訪問介護で担当していたある利用者様は、私が帰宅しようとするタイミングで、決まって「胸が苦しい」と訴える方でした。
最初のうちは毎回慌てて救急車を呼ぶべきか迷いましたが、何度か経験するうちに、それは私が帰ってしまうことへの寂しさから来る、精神的な訴えであることが分かってきました。
このようなケースへの初期対応として、以下のステップを踏むことが重要です。
- まずは訴えを真摯に受け止める:
「どうせ嘘だろう」という態度を取るのは絶対にいけません。「どうされましたか?」「どこが痛みますか?」と、まずは相手の訴えに真剣に耳を傾ける姿勢を見せます。 - 客観的な観察と事実確認を行う:
血圧や体温、脈拍、血中酸素飽和度などのバイタルサインを測定し、客観的なデータを確認します。顔色や呼吸の状態なども注意深く観察します。この行動自体が、相手に「ちゃんと見てもらえている」という安心感を与える効果もあります。 - 安心させる言葉をかけ、次の約束をする:
バイタルサインなどに明らかな異常がない場合は、「血圧も正常ですし、大丈夫ですよ」と客観的な事実を伝えて安心させます。その上で、「きっと疲れが出たのかもしれませんね。少し横になって休みましょうか」「次は〇曜日に必ず来ますからね」など、具体的な行動や次の約束を提示することで、相手の不安を和らげることができます。
依存心の強い高齢者や、病気アピールが多い方への対応は、根気が必要です。
しかし、その訴えの裏には、身体的な苦痛ではなく、精神的な寂しさや不安が隠れていることが多いのです。
そのSOSを見抜き、適切に対応することが、私たち専門職に求められるスキルと言えるでしょう。
老人のかまってちゃんを上手に「無視」する、プロの対処法5選
ここまで、「かまってちゃん」と呼ばれる高齢者の心理や、その行動の背景にある原因について見てきました。
彼らの行動が、孤独や不安、あるいは病気のサインかもしれないと理解するだけで、少しだけ冷静に向き合えるようになったのではないでしょうか。
しかし、理解はできても、現実問題として、一人の利用者さんにばかり時間を割くわけにはいきません。
あなたの心と体を守り、他の利用者さんにも公平なケアを提供するためには、具体的な「対処法」が必要です。
ここで言う「無視」とは、相手を拒絶し、尊厳を傷つけるような完全な無視ではありません。
そうではなく、相手の要求や言動をすべて真正面から受け止めるのではなく、上手に受け流し、戦略的に距離を置くためのプロフェッショナルな技術としての「無視」です。
この技術は、相手のためでもあり、何よりもあなた自身が介護の仕事で燃え尽きないために、絶対に身につけておくべきスキルです。
それでは、私が様々な介護現場で実践し、効果があった5つの対処法をご紹介します。

【対処法①】肯定も否定もしない。聞き流す「傾聴」コミュニケーション術
「かまってちゃん」への対応で最もやってはいけないのが、相手の話に深入りし、議論をしたり、アドバイスをしたりすることです。
彼らが求めているのは、解決策ではなく、「話を聞いてもらえること」そのものだからです。
ここで役立つのが、「聞き流す」技術です。
これは、相手に失礼な態度を取るのではなく、相手の感情に寄り添いながらも、話の内容には巻き込まれない、高度なコミュニケーション術です。
あいづちは「そうなんですね」を基本にする
相手の話に対して、「はい」「いいえ」で答えてしまうと、会話が続いてしまいます。
そうではなく、「そうなんですね」「なるほど」「さようでございますか」といった、肯定も否定もしない、ニュートラルな相槌を使いましょう。
これにより、話を聞いている姿勢は見せつつも、会話を広げないようにコントロールできます。
相手の言葉を繰り返す「オウム返し」
相手が言った言葉の一部を、そのまま繰り返すテクニックです。
例えば、利用者さんが「昨日は腰が痛くて眠れなかったのよ」と言ったら、「腰が痛くて眠れなかったのですね」と返します。
これにより、相手は「私の言っていることを理解してくれている」と感じ、満足感を得やすくなります。
職員側は、自分の意見を言う必要がないため、精神的な負担が少なくて済みます。
焦点を「事実」ではなく「感情」に当てる
話の内容が延々と続く自慢話や愚痴だったとしても、その「事実」に付き合う必要はありません。
注目すべきは、その話をしている相手の「感情」です。
「それはお辛かったですね」「昔はすごかったのですね」と、相手の感情にだけ寄り添う言葉をかけます。
これにより、相手の承認欲求や共感してほしいという気持ちを満たし、話を短時間で切り上げやすくなります。
この「聞き流す傾聴」は、相手を傷つけずに自分のペースを守るための、非常に有効なバリアになります。
【対処法②】「1分だけお話を伺いますね」時間で区切る約束のルール
終わりが見えない会話ほど、精神的に疲れるものはありません。
特に、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)のように、比較的お元気な方が多い職場では、一度捕まると30分、1時間と長話になってしまうことも珍しくありませんでした。
そこで効果的なのが、物理的に時間を区切るというルールです。
対応の最初に、「〇〇さん、今から1分だけなら、お話伺えますよ」と、明確に時間を宣言するのです。
スマートフォンやキッチンタイマーを取り出して、「では、タイマーをセットしますね」と、目に見える形で時間を示すのも有効です。

なぜ時間を区切る必要があるのかを伝える
ただ一方的に「1分だけです」と言うと、冷たい印象を与えかねません。
「この後、皆さんの配茶の準備をしないといけないので、1分だけいいですか?」
「次のお部屋に巡回に行く時間なので、申し訳ありません」
というように、客観的で、誰もが納得できる理由を添えることがポイントです。
あなた個人の都合ではなく、「業務だから仕方ない」という形にすることで、相手も受け入れやすくなります。
時間が来たら、毅然とした態度で切り上げる
そして最も重要なのが、約束の時間が来たら、たとえ話の途中であっても、きちんと切り上げることです。
タイマーが鳴ったら、「あ、お約束の時間ですね。お話の続きは、また後で伺いますね」と、にこやかに、しかし毅然とした態度でその場を離れます。
ここで「もう少しだけ…」という相手の要求に応じてしまうと、このルールは全く意味がなくなってしまいます。
「また後で」と次があることを示唆することで、相手の喪失感を和らげる効果もあります。
この方法は、利用者さんに対して「あなたは特別な存在ではない。他の皆さんと同じように、限られた時間の中で対応しています」という公平性を示すことにも繋がり、特定の職員への依存を防ぐ効果も期待できます。
【対処法③】一人で抱えない!チームで対応方針を共有する重要性
「かまってちゃん」への対応で最も危険なのは、真面目で優しい職員が、たった一人でその負担を抱え込んでしまうことです。
あなたが一人で耐えれば耐えるほど、利用者さんはあなたに依存し、問題は深刻化していきます。
この問題を解決するための最も強力な方法は、チーム全体で対応方針を統一し、情報を共有することです。
私が施設の事務員として介護記録を毎日見ていると、誰がどの利用者さんに多くの時間を費やしているかは、手に取るように分かります。
優れた介護チームは、「Aさん(特定の利用者さん)の対応は、優しいBさん(特定の職員)にお願いしよう」とは考えません。
そうではなく、「Aさんのこの言動には、チーム全員でこのように対応しよう」という共通認識、つまり「対応マニュアル」を頭の中に持っているのです。

なぜ情報共有が不可欠なのか?
もし、職員によって対応がバラバラだったらどうなるでしょうか?
A職員は話を長く聞いてくれるけれど、B職員はすぐに話を切り上げてしまう。
そうなると、利用者さんは当然、自分の要求を一番聞いてくれるA職員に集中的にアプローチするようになります。
これでは、A職員が疲弊してしまうのは目に見えています。
チームで対応を統一することで、特定の職員への負担の集中を防ぐことができるのです。
何を、どうやって共有するのか?
共有すべき情報は、単なる愚痴や悪口ではありません。
- その方の言動の背景にあると思われる原因(孤独感、病気の可能性など)
- これまで試してみて、効果があった対応方法
- 逆に、失敗してしまった対応方法
- 「この言葉をかけると落ち着かれる」といった具体的な声かけ
これらの情報を、日々の申し送りや介護記録、あるいは定期的なカンファレンス(話し合いの場)で、スタッフ全員が共有します。
そうすることで、誰が対応しても、一貫性のある質の高いケアを提供できるようになるのです。
「あの人への対応は、私一人が我慢すればいい」という考えは、今すぐ捨ててください。
それはチームとしての責任放棄であり、長い目で見れば、あなた自身とチーム全体のケアの質を低下させることに繋がります。
【対処法④】イライラしたら負け。自分の感情を客観視するストレスケア
どんなにテクニックを駆使しても、理不尽な要求や終わらない話に、イライラしてしまうことはあるでしょう。
人間ですから、それは当然の感情です。
大切なのは、そのイライラという感情に、あなた自身が振り回されないことです。
怒りの感情のピークは、長くて6秒と言われています。
つまり、この6秒間をやり過ごすことができれば、衝動的な言動を抑えることができるのです。
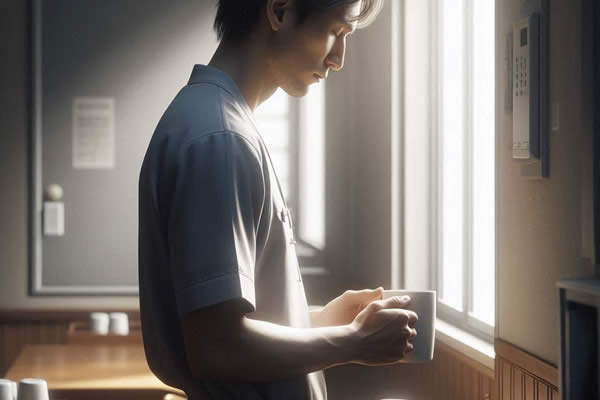
心の中で「6秒」数える
利用者さんの言葉にカチンときたら、すぐに言い返したり、態度に出したりする前に、まずは深呼吸をして、心の中でゆっくりと「1、2、3、4、5、6」と数えてみてください。
これだけで、冷静さを取り戻すきっかけになります。
物理的にその場を離れる
もし可能であれば、一旦その場を離れるのが最も効果的です。
「すみません、お手洗いに行ってきます」「ちょっとお茶を飲んできます」など、理由をつけて数分間だけでもその場から離れましょう。
物理的に距離を取ることで、気持ちをリセットすることができます。
自分の感情を「実況中継」する
イライラしてきたら、心の中で「お、自分、今イライラしてるな」「この言葉に反応して、心拍数が上がってきたぞ」というように、自分の感情や身体の変化を客観的に実況中継してみてください。
自分の感情を他人事のように眺めることで、感情に飲み込まれるのを防ぐことができます。
これはアンガーマネジメントの基本的なテクニックの一つです。
あなたの心が穏やかでなければ、良い介護はできません。
利用者さんのために頑張るのと同じくらい、あなた自身の心の健康を守るためのセルフケアを意識することが、プロとして長く働き続けるための秘訣です。
【対処法⑤】在宅介護で親がかまってちゃんになった時の距離の置き方
これまでの話は、主に介護施設で働く職員向けのものでした。
しかし、この問題は、ご自宅で親の介護をされている方にとっても、非常に深刻です。
むしろ、24時間365日、逃げ場のない在宅介護のほうが、精神的な負担は大きいかもしれません。
家族だからこその遠慮のなさや甘えが、言動をさらにエスカレートさせることもあります。
在宅介護で親が「かまってちゃん」になってしまい、「うざい」とまで感じて疲弊している方は、まず「一人で抱え込まない」ことを徹底してください。

外部のサービスを積極的に利用する
「親の面倒は、家族が見るべきだ」という考えに縛られていませんか?
デイサービスやショートステイといった介護保険サービスは、あなたのためにこそあるのです。
週に1日、2日でも、親と物理的に離れる時間を作ることで、あなたの心に余裕が生まれます。
その余裕が、結果的に親に対して優しく接することに繋がるのです。
意識的に「介護者」の役割から離れる
在宅介護では、常に「介護する側」と「される側」という役割に固定されがちです。
意識的に、その役割から離れる時間を作りましょう。
自分の趣味に没頭する時間、友人とランチに行く時間など、「ただの自分」に戻れる時間を確保することが、精神的なバランスを保つ上で非常に重要です。
ケアマネージャーを「チームの仲間」にする
施設でのチーム対応と同じように、在宅介護でもチームを作ることができます。
あなたの最も強力な仲間は、担当のケアマネージャーです。
親の言動で困っていること、あなたの負担が限界に近いことなどを、正直に相談してください。
ケアマネージャーは、サービスの調整だけでなく、あなたの精神的なサポートや、親への適切なアプローチ方法を一緒に考えてくれる専門家です。
家族だからこそ、距離を置くことには罪悪感が伴うかもしれません。
しかし、共倒れになってしまっては、元も子もありません。
あなたが笑顔でいることこそが、最高の親孝行なのだと考えて、上手に外部の力を借りる勇気を持ってください。
まとめ:「老人のかまってちゃん」を無視する以外の道
今回は、介護現場で多くの職員が頭を悩ませる「かまってちゃん」と呼ばれる高齢者への対応について、その心理的な背景から具体的な対処法までを詳しく解説しました。
彼らの行動の裏には、単なるわがままではなく、深い孤独や不安、あるいは認知症などの病気が隠れていることが少なくありません。
だからこそ、感情的に老人のかまってちゃんを無視するという選択は、あなたと相手の双方を追い詰めるだけの結果になりがちです。
この記事で提案した5つの対処法は、相手を拒絶するためのものではありません。
時間を区切る、チームで対応を統一する、聞き流す技術を駆使するといった方法は、むしろあなた自身を守り、プロとして質の高いケアを継続するための「戦略的な距離の置き方」なのです。
大切なのは、相手を理解しようと努めながらも、決して一人で抱え込まないこと。
そして、自分の心を守るための技術を身につけることです。
今日から試せるテクニックを一つでも実践し、あなたの心が少しでも軽くなることを、心から願っています。




コメント