「ユニット型特養って、人間関係が濃密で理想のケアができそうだけど、なんだかきついって聞くな…」
「仕事内容そのものがハードなのか、それとも閉鎖的な人間関係が原因なんだろうか…」
今、まさにあなたも同じような疑問や不安を抱えているのではないでしょうか。
かつて様々な介護施設を渡り歩き、現在は施設の事務方として現場を見守る私からすれば、その悩み、痛いほどよく分かります。

結論から言うと、ユニット型特養がきついと言われる原因は、仕事内容と人間関係、その両方が複雑に絡み合った根深い問題点にあります。
この記事を最後まで読めば、その「きつさ」の正体が明確になり、あなたが今どうすべきか、具体的な次の一歩が見えてくるはずです。
ユニット型特養がきついと言われる5つの理由【仕事と人間関係の闇】
ユニット型特養が提供する「家庭的な雰囲気の中での個別ケア」という言葉は、非常に魅力的に聞こえます。
しかし、その理想的な響きの裏側には、現場の介護職員を疲弊させる構造的な問題が潜んでいることが多いのです。
ここでは、私が多くの施設を見てきた経験から、ユニット型特養がきついと言われる5つの具体的な理由を、仕事内容と人間関係の両面から深掘りしていきます。

そもそもユニット型特養とは?従来型との決定的な違い
まず、なぜユニット型特養特有の「きつさ」が生まれるのかを理解するために、従来型の特養との違いを明確にしておきましょう。
従来型特養との比較
従来型の特別養護老人ホームは、広いフロアに多くのベッドが並ぶ「多床室」が主流でした。
そこでの介護は、どうしても流れ作業的になりがちです。
決まった時間に一斉に食事をし、決まった順番で入浴する。
いわば「集団ケア」が中心で、職員はフロア全体を常に動き回り、多くの利用者を同時に見る必要がありました。
ユニット型特養の理想
一方、ユニット型特養は、10人程度の少人数のグループを「1ユニット」として、それぞれに専用の居住空間(個室とリビングなどの共用スペース)が割り当てられています。
ここでの理想は、まさに入居者一人ひとりの生活リズムや個性を尊重した「個別ケア」の実践です。
朝起きる時間も、食事の時間も、その人らしく。
まるで自宅にいるような、家庭的な雰囲気を目指すのがユニットケアの基本理念です。
聞こえは非常に良いですよね。
しかし、この「個別ケア」と「家庭的な雰囲気」という理想が、皮肉にも現場の職員を追い詰める要因の一つになっているのです。
私が従来型の特養からユニット型の施設へ初めて移った時、そのギャップに戸惑ったことを今でも覚えています。
集団ケアの効率性とは全く違う、一人ひとりに寄り添うことの難しさと責任の重さを痛感しました。
【仕事内容】実質的なワンオペ?ユニット型特養の孤独な働き方
ユニット型特養の仕事内容における最大の特徴は、特定の時間帯において「ワンオペ」状態になりやすいことです。
1ユニット(利用者10人前後)を、職員1人だけで担当する時間帯が、早番や遅番、特に夜勤では当たり前のように存在します。

一人でこなす業務の範囲
このワンオペ時間帯に、職員は何をするのでしょうか。
食事の準備や配膳、食事介助、そして口腔ケア。
トイレへの誘導やオムツ交換といった排泄介助。
ナースコールの対応。
さらには、ユニット内の簡単な調理や掃除、洗濯、そして介護記録の入力まで。
文字通り、そのユニット内で起こるすべてのことに一人で対応しなくてはなりません。
私がいた有料老人ホームでは、介護、看護、調理、清掃と役割が分担されていることが多かったですが、ユニット型特養ではこれら全てを一人で担う場面が出てきます。
これは、マルチタスク能力が求められると言えば聞こえは良いですが、現実には凄まじい業務量です。
相談相手のいない孤独感
肉体的な負担以上に精神的にこたえるのが、この「孤独感」です。
利用者の体調に変化があった時、転倒などのアクシデントが起きた時、その場で判断を下さなければならないのは自分一人。
すぐに相談できる同僚は、すぐ隣にはいません。
他のユニットに応援を頼むこともできますが、相手も同じく手一杯の状況であることがほとんど。
「迷惑をかけてはいけない」という気持ちが働き、結局一人で抱え込んでしまう。
この精神的なプレッシャーと孤独こそが、ユニット型特養の仕事がきついと感じさせる大きな要因なのです。
【人間関係】閉鎖空間が助長する、職員間の根深い対立といじめ
仕事内容のきつさに拍車をかけるのが、ユニット型特養特有の人間関係の問題です。
「家庭的な雰囲気」を目指す少人数の閉鎖的な環境は、一度人間関係がこじれると、逃げ場のない息苦しい空間へと変貌します。

「ユニット」という名の閉鎖空間
ユニットのスタッフは、基本的にメンバーが固定されています。
毎日同じ顔ぶれで、濃密な時間を共に過ごすわけです。
これは相性が良ければ最高のチームになりますが、逆の場合は悲劇です。
介護観の違い、仕事の進め方への不満、あるいは単なる性格の不一致。
そういった小さな亀裂が、閉鎖された空間の中で増幅され、根深い対立に発展しやすいのです。
従来型の特養であれば、フロアには多くの職員がいて、苦手な人がいても他の職員と関わることで気持ちを紛らわせることもできました。
しかし、ユニット内ではそれができません。
ユニット間の対立と職員の孤立
さらに厄介なのが、「お隣のユニットとの対立」です。
「うちのユニットの方がちゃんとやっている」「あそこのユニットは楽をしている」といった、さながらご近所トラブルのような感情的な対立が生まれやすいのも特徴です。
そして、そのユニット内で一人がターゲットにされると、いじめに発展するケースも少なくありません。
少人数であるがゆえに、一度「あの人は使えない」というレッテルを貼られてしまうと、ユニット内で孤立し、精神的に追い詰められてしまうのです。
「家庭的な雰囲気」という理想が、いつの間にか「家庭内に漂う冷戦状態」のようになってしまう。
これは、残念ながら多くのユニット型施設で見られる、介護現場の「あるある」な矛盾点の一つと言えるでしょう。
責任だけが重い…精神的に追い詰められるユニットリーダーの苦悩
ユニットケアを円滑に進める上で、非常に重要な役割を担うのが「ユニットリーダー」です。
しかし、このユニットリーダーという立場こそ、ユニット型特養のきつさを象徴していると言っても過言ではありません。
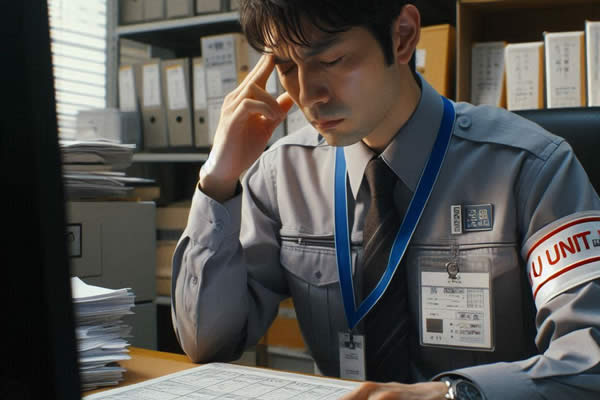
中間管理職としての板挟み
ユニットリーダーは、現場の介護業務をこなしながら、ユニット全体のマネジメントも行います。
具体的には、
- ユニット職員のシフト作成や業務調整
- 新人職員への指導・教育
- 利用者の家族への対応やカンファレンスの開催
- 施設長やケアマネージャーなど、他部署との連携・報告
など、その業務は多岐にわたります。
まさに、現場と運営の板挟みになる中間管理職です。
現場の職員からは「もっと人を増やしてほしい」と突き上げられ、上層部からは「今の人数で何とかしろ」とプレッシャーをかけられる。
この構図は、どの業界でも同じかもしれませんね。
権限なき責任の重圧
問題なのは、多くの施設でリーダーに十分な権限が与えられていないにもかかわらず、責任だけが非常に重いという点です。
人事権や予算に関する決定権はなく、できることは限られている。
それなのに、ユニット内で何か問題が起これば、全責任を負わされる。
私が現在勤める施設の事務方から見ていても、リーダーたちが現場の職員と運営側の意向との間で疲弊していく様子は手に取るように分かります。
リーダー手当は微々たるものであることが多く、その負担と報酬が見合っていないのが現実です。
この「報われない感」が、リーダーたちの精神を蝕んでいくのです。
理想のケアはどこへ?人員不足でユニット型特養が崩壊する現実
ここまで挙げてきた問題の根底にあるのは、多くの場合、慢性的な「人員不足」です。
どんなに素晴らしい理想を掲げても、それを実現するための「人」がいなければ、絵に描いた餅にすぎません。
ユニットケアという理念が、理想通りに機能していない施設は少なくありません。

本来であれば、利用者一人ひとりのペースに合わせたケアを行うはずが、人員が足りないために、結局は時間に追われる流れ作業にならざるを得ないのです。
朝は時間内に全員を起こして着替えさせ、食事介助をし、排泄介助に走り回る。
これでは、やっていることは従来型の集団ケアと何ら変わりません。
むしろ、建物の構造上、職員の動線が長く非効率で、従来型よりも身体的な負担が大きいことさえあります。
個別ケアという理想を信じて入職したにもかかわらず、現実はただの「小分けにされた集団ケア」。
この理想と現実のギャップこそが、職員のモチベーションを奪い、「こんなはずじゃなかった」と辞めていく大きな原因です。
そして、人が辞めればさらに人員は不足し、現場はますます疲弊していく。
この負のスパイラルによって、ユニット型特養の理念そのものが崩壊の危機に瀕している現場も、残念ながら存在するのです。
ユニット型特養のきつい現状を乗り越えるための具体的対処法
ここまでユニット型特養のきつい現実についてお話ししてきましたが、「じゃあ、もう辞めるしかないのか」と絶望する必要はありません。
きつい現状を少しでも改善し、自分自身を守るための具体的な対処法は存在します。
ここでは、今の職場で働き続けるための考え方のコツから、いざという時のための他の選択肢まで、幅広く解説していきます。

今の職場で楽になるには?人間関係と仕事の負担を減らす考え方
まず試してみてほしいのが、考え方や仕事のやり方を少しだけ変えてみることです。
環境を変えるのは大変ですが、自分の意識を変えることは今日からでも始められます。
人間関係の極意:「課題の分離」と「期待しない」こと
ユニット内の濃密な人間関係に疲れたら、「課題の分離」という考え方を試してみてください。
これは、「自分の課題」と「他人の課題」を切り離して考える方法です。
例えば、特定の同僚がいつも不機嫌なのは、その同僚の課題であって、あなたの課題ではありません。
あなたがその人の機嫌を取る必要はないのです。
「私は私の仕事をきちんとやるだけ」と割り切ることで、精神的な負担はかなり軽くなります。
また、相手に「変わってほしい」と期待するのをやめるのも有効です。
他人を変えるのは非常に困難ですが、自分の捉え方を変えることはできます。
「あの人はそういう人なんだ」と、ある種の諦めにも似た感覚で受け入れることで、無駄なエネルギーを使わずに済みます。
仕事の負担を減らす工夫:「完璧なケア」の呪縛から逃れる
ユニットケアの理想は「完璧な個別ケア」かもしれませんが、それを100%実践しようとすると、必ずどこかで無理が生じます。
特に人員が不足している状況では不可能です。
大切なのは、「良い加減」で仕事に優先順位をつけること。
「絶対にやらなければならないこと(利用者の生命や安全に関わること)」と、「できればやった方が良いこと(+αのケア)」を自分の中で区別するのです。
全てを完璧にこなそうとせず、「今日はここまでできれば十分」と自分を許してあげることが、長く働き続けるためには不可欠です。
私が様々な施設を渡り歩いて学んだのは、真面目で責任感の強い人ほど、この「完璧」の呪縛に苦しみ、燃え尽きてしまうという事実です。
あなたの職場は大丈夫?人員配置基準と平均から見る労働環境
自分の職場が客観的に見てどうなのかを知ることも、重要な対処法の一つです。
感情的に「きつい」と感じるだけでなく、客観的な指標と比べることで、今の状況が妥当なのか、それとも異常なのかを判断できます。
その指標となるのが「人員配置基準」です。

知っておきたい「人員配置基準」という最低ライン
介護施設の人員配置は、介護保険法によって最低基準が定められています。
ユニット型特養の場合、国の基準では、
- 日中:利用者と介護・看護職員の比率が「3:1」以上(常勤換算)
- 夜間・深夜:ユニットごとに1人以上の介護職員または看護職員
とされています。
重要なのは、これが「最低基準」であるという点です。
つまり、法律上はこれさえ満たしていれば良い、ということになります。
あなたの職場が、この最低基準ギリギリで運営されているのか、それとも余裕を持った人員配置がなされているのか。
これを把握するだけでも、施設の体質が見えてきます。
平均的な人員配置との比較
実際には、多くの施設がこの基準以上の人員を配置しようと努力しています。
ユニット型特養における職員の平均的な配置は、日中の利用者と職員の比率が2.5:1や2:1に近い施設もあります。
もしあなたの職場が、慢性的に3:1ギリギリで、誰かが休むとすぐに現場が回らなくなるような状態であれば、それは経営側の問題であり、あなたが「きつい」と感じるのは当然なのです。
事務職として労務管理に関わる今だからこそ言えますが、求人票を見る際や面接の際に、具体的な人員配置の状況(特に夜勤体制や日中の繁忙時間帯の人数)を質問することは、ブラックな職場を避けるための非常に有効な手段です。
特養の仕事が覚えられない新人さんへ。焦らないための思考法
特に新人職員にとって、ユニット型特養の環境は戸惑うことが多いかもしれません。
「特養の仕事がなかなか覚えられない」と悩んでしまうのは、あなただけではありません。

覚えられないのは「環境」のせいかもしれない
ユニット型は、少人数で業務を回すため、つきっきりで仕事を教えてもらえる時間が少ない傾向にあります。
OJT(オンザジョブトレーニング)と言えば聞こえは良いですが、実際には「見て覚えろ」というスタイルになりがちです。
また、ユニットごとに仕事のやり方やルールが微妙に違う「ローカルルール」が存在することも、新人が混乱する原因になります。
仕事が覚えられないのを、自分の能力不足のせいだと責めないでください。
多くの場合、それは個人の問題ではなく、教育体制が整っていないという「環境」の問題なのです。
焦りをなくす具体的なアクション
では、どうすれば良いか。
まずは、メモの取り方を工夫することです。
ただ言われたことを書くのではなく、「なぜそうするのか」という理由も一緒にメモしておくと、応用が利くようになります。
そして、質問する時間をもらうこと。
忙しい時間帯を避け、「今、5分だけよろしいですか?」と時間を区切って質問すれば、先輩も対応しやすいはずです。
何よりも大切なのは、一度に全てを覚えようとしないこと。
介護の仕事は非常に幅広く、一朝一夕で身につくものではありません。
「今日はこれだけは確実にできるようになった」と、小さな成功体験を積み重ねていくことが、焦りをなくし、着実な成長につながります。
デイサービスと特養はどっちが大変?他の介護施設との比較
「もう、ユニット型特養は自分には向いていないかもしれない…」。
そう感じた時、視野を広げて他の介護施設のことを知っておくのは、非常に重要です。
特養だけが介護の職場ではありません。
「デイサービスと特養、どっちが大変なんだろう?」と考えたことがある人もいるでしょう。
結論から言うと、大変さの種類が全く異なります。
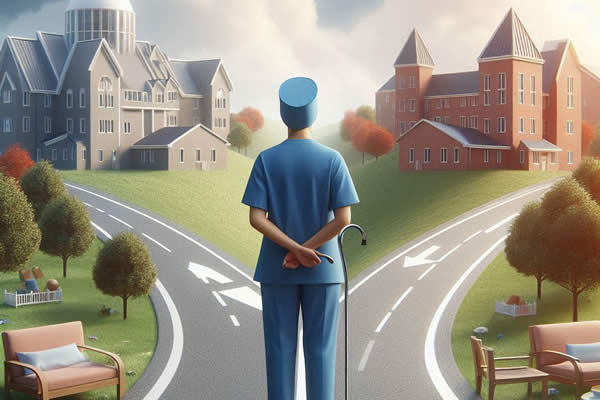
特養以外の介護施設の選択肢
- デイサービス(通所介護):
夜勤がなく、基本的にカレンダー通りの休みが取りやすいのが特徴です。身体的な負担は特養より軽い傾向にありますが、利用者を楽しませるためのレクリエーションの企画力やコミュニケーション能力がより求められます。 - 有料老人ホーム:
施設によってコンセプトが様々ですが、接遇マナーが重視される傾向にあります。介護業務が分業化されていることも多く、一つの業務に集中したい人には向いているかもしれません。 - サービス付き高齢者向け住宅(サ高住):
比較的自立度の高い利用者が多く、主な仕事は安否確認や生活相談です。身体介護の場面は少ないですが、緊急時の対応力や判断力が求められます。
このように、施設形態によって仕事内容も求められるスキルも大きく異なります。
私が様々な施設を渡り歩いた経験から言えるのは、「楽な職場」というものは存在しないが、「自分に合った職場」は必ずある、ということです。
ユニット型特養のきつさが「ワンオペの孤独感」や「閉鎖的な人間関係」にあると感じるなら、よりチームで動く従来型の施設や、人の入れ替わりが多いデイサービスの方が、あなたにとっては働きやすい環境かもしれません。
それでも特養の仕事が楽しいと思える瞬間と、向いている人の特徴
ここまで厳しい側面を多くお伝えしてきましたが、もちろん、ユニット型特養の仕事には素晴らしいやりがいや楽しさもあります。
でなければ、多くの職員が働き続けるはずがありません。
特養の仕事が楽しいと感じる瞬間は、やはり利用者との深い関係性を築けた時です。
ユニットケアだからこそ、一人ひとりの人生に深く寄り添い、その人らしい最期を看取る(看取りケア)ことさえあります。
ご家族から「あなたに担当してもらえて本当に良かった」と涙ながらに感謝された時の感動は、何物にも代えがたいものです。

ユニット型特養に向いている人とは?
こうした経験から、ユニット型特養の仕事に向いている人の特徴も見えてきます。
- マイペースで自己管理能力が高い人:
一人で黙々と作業を進めるのが苦にならず、自分で仕事の段取りを組み立てられる人。 - 少人数での深い関係構築が得意な人:
大人数でワイワイするより、特定の人とじっくり向き合うのが好きな人。 - 観察力があり、小さな変化に気づける人:
利用者のちょっとした表情や様子の変化から、その人のニーズを汲み取れる人。 - 精神的に自立している人:
他人の言動に一喜一憂せず、自分の軸をしっかり持てる人。
もしあなたがこれらの特徴に当てはまるなら、たとえ今きついと感じていても、ユニット型特養はあなたにとって「天職」になる可能性を秘めています。
まとめ:ユニット型特養がきついと感じたら考えるべきこと
今回は、ユニット型特養がきついと言われる理由を「仕事内容」と「人間関係」の両面から深掘りし、その具体的な対処法まで解説してきました。
最後に、この記事の要点を振り返ります。
- ユニット型特養のきつさは、理想の「個別ケア」と現実の「人員不足」のギャップから生まれる。
- 仕事内容の面では、「実質的なワンオペ」による肉体的・精神的負担が大きい。
- 人間関係の面では、「閉鎖的な環境」が対立やいじめを助長しやすい。
- 現状を乗り越えるには、「考え方を変える」「客観的に職場を分析する」「他の選択肢を知る」ことが重要。
今、あなたが感じている「きつい」という気持ちは、決してあなたの能力不足や甘えが原因ではありません。
それは、ユニットケアが抱える構造的な問題に、あなたが真面目に向き合っている証拠なのです。
この記事を読んで、まずはご自身の状況を客観的に見つめ直してみてください。
そして、今日から試せる小さな工夫を始めてみましょう。
それでも心が晴れないのなら、それはあなたが次のステージに進むべきサインなのかもしれません。
あなたには、ユニット型特養以外にも活躍できる場所がたくさんあります。
今回の記事が、あなたの苦しみを和らげ、より良いキャリアを築くための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。

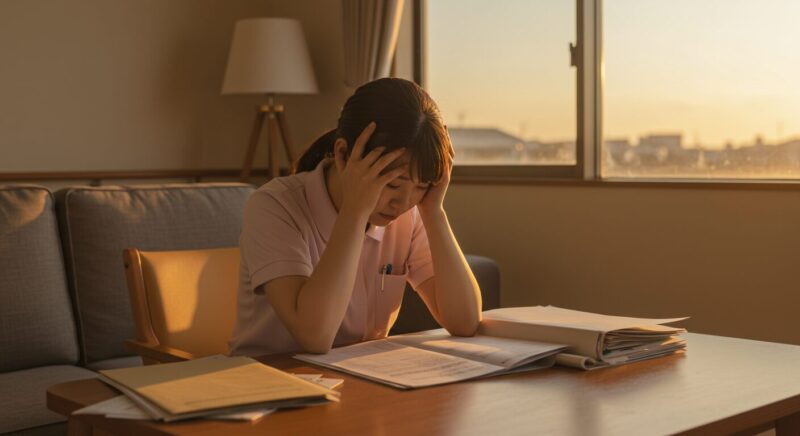


コメント